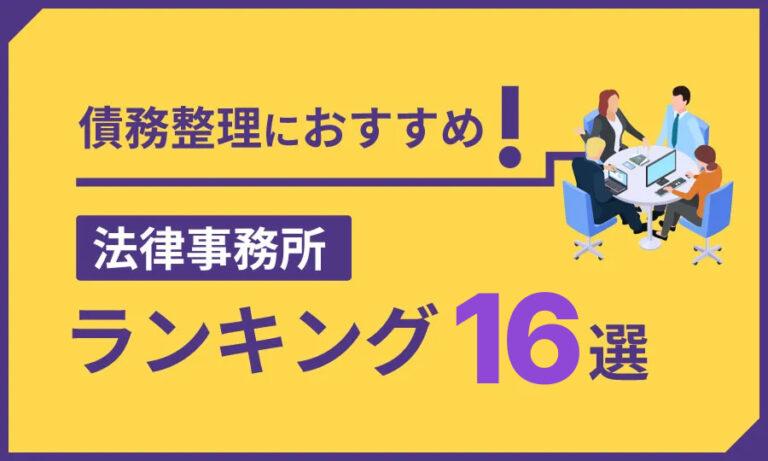財団債権とは?優先順位や弁済方法などをわかりやすく解説

債権者の破産者に対する債権(財産上の請求権)は、破産債権と財団債権に分けられます。財団債権は、破産手続によらずに随時弁済を受けられる債権です。破産手続においては、債権の優先順位や弁済方法を理解していなければ、弁済の見込みや時期なども把握できません。
今回は、財団債権とは何かを理解するために、財団債権の具体例や優先順位、弁済方法、破産債権との違いなどをわかりやすく解説します。破産手続における債権の分類について理解を深めるのにご活用ください。
財団債権とは破産手続によらず随時弁済を受けられる債権
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです(破産法2条7項)。
財団債権以外の債権(破産債権)は、破産手続の配当で債権額に応じて弁済されます。財団債権は、配当手続きを待たず破産債権に優先して弁済を受けられます。破産債権が弁済されるのは、財団債権を弁済しても余りがある場合だけです。
財団債権に分類される債権には複数の種類があり、それぞれに優先順位も存在します。ここでは、財団債権の具体例、財団債権の優先順位、弁済方法を解説します。
それぞれ順に解説いたします。
財団債権の2つの具体例

財団債権は、法的性質によって次の2つに分けられます。
- 本来的財団債権
- 政策的財団債権
本来、財団債権が破産債権よりも優先されるのは、破産手続を進めるのに必要不可欠な費用であるためです。この本来の意味での財団債権としての性質を持つ債権を、本来的財団債権と言います。
政策的財団債権は、本来は破産債権に分類される性質の債権を政策的な配慮から財団債権とされたものです。たとえば、破産者の使用人の給料は、破産手続開始前に発生しているもので破産手続を進めるのに必要な費用とは言えませんが、労働者保護という政策的な配慮から財団債権とされています(破産法149条1項)。
本来的財団債権は破産手続きに必要不可欠な費用の債権
本来的財団債権の具体例は、次のとおりです。
破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破産法148条1項1号)
破産手続の申立費用、債権者集会開催にかかる費用など
破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権(同項2号)
破産管財人の報酬など
破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(同項4号)
破産管財人が業務のために第三者と契約した際の相手方の債権など
事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(同項5号)
破産手続開始後に、第三者が義務なく破産財団に属する建物の修繕をした際の修理費用など
委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(同項6号)
破産手続開始によって委任契約が終了した後に、受任者が破産管財人に事務を引き継ぐ前に行った事務処理の費用など
破産法第53条第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権(破産法148条7号)
破産手続開始時に未履行の売買契約について、破産管財人が商品を受け取った場合における相手方の代金請求権など
破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れがあった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権(同項8号)
破産手続の開始から雇用契約終了までの給料債権など
政策的財団債権は一部の公租公課や労働債権
政策的財団債権の具体例は、次のとおりです。
- 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの(破産法148条1項3号)
- 破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権(同法149条1項)
- 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権のうち、退職前3月間の給料の総額に相当する額(同条2項)
公租公課や労働債権は、破産手続に必要な費用ではありませんが、租税徴収や労働者保護という政策的配慮から財団債権に分類されています。
財団債権の優先順位
破産財団の状況によっては、財団債権をすべて弁済できないケースもあります。破産財団の財産がすべての財団債権を弁済するのに足りないときは、次の優先順位で弁済されます(破産法152条)。
それぞれについて、具体的な内容と優先して弁済される理由を解説します。
1. 破産管財人への報酬
破産管財人への報酬は、何よりも優先して弁済を受けられます。
破産管財人の報酬は、破産財団の一部と引継予納金で構成されます。破産財団の財産が確保されるのは、破産管財人の換価業務の結果によるものです。破産財団の規模を大きくするには、その分だけ破産管財人の業務も多くなります。
破産管財人への報酬が優先されるのは、破産財団の規模に応じた報酬を保障することで、破産管財人が安心して破産手続を進められるためと言えるでしょう。
2. 債権者申立て又は第三者予納の予納金補填
法人の破産手続は、破産者だけでなく債権者による申立ても可能です。債権者が破産申立てをしたときには、破産者ではなく債権者が予納金を納付します。
破産財団から破産管財人への報酬を支払っても余剰があるときには、他の財団債権に優先して債権者の支払った予納金が返還されます。ただし、債権者申立ての場合、破産管財人の業務に債務者が協力することは期待できず、財産の調査や換価処分がスムーズに行えないケースもあるでしょう。そのため、債権者の予納金を返還するのに十分な破産財団を形成できないことも少なくありません。
3. 裁判の費用や管理・換価・配当費用の請求権
破産手続を進行するためには、申立費用や債権者集会を開催するための費用、破産手続開始決定の公告費用など、さまざまな費用がかかります(破産法148条1項1号・2号)。
破産手続の進行に必要な費用を確保しなければ手続きを進行できないため、これらの費用は「その他の財団債権」よりも優先して支払われます。
4. その他の財団債権
先に挙げた3つの項目に含まれない財団債権は、財団債権の中では優先順位が一番下となります。
政策的財団債権に当たる公租公課や労働債権は、その他の財団債権です。破産財団が同順位の財団債権を弁済するのに足りないときには、債権額に応じて弁済されます(破産法152条1項)。
財団債権の弁済方法は随時全額の支払いを受けられる
財産債権の弁済は、破産債権に優先して随時全額が支払われます(破産法151条)。財団債権の債権者は、破産開始決定後、破産管財人に財団債権を有する旨とその内容を申し出ることで、弁済を受けられます。
ただし、財団債権であっても、全額の弁済が保障されているわけではありません。破産財団が財団債権すべてを弁済できないときには、優先順位に従って弁済されます。優先順位が同順位の財団債権があるときには、債権額に応じて按分した額が弁済されます。
破産管財人が財団債権を承認するに際しては、裁判所の許可が必要です(破産法78条2項13号)。ただし、財団債権の額が100万円以下のときには裁判所の許可は不要となっており(破産法規則25条)、申し出があった債権について、管財人口座から随時弁済が行われます。
(財団債権の取扱い)
第百五十一条 財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。
引用元 e-Gov法令検索|破産法
財団債権と破産債権の違いは?
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、財団債権に該当しない債権のことです(破産法2条5項)。
たとえば、銀行からの借入金や、取引先の買掛金、外注費、財団債権に属しない労働債権など、会社を経営するうえで発生する債権は、ほとんどが破産債権です。
破産債権は、財団債権とは異なり、配当手続きを経なければ弁済を受けることができません。配当では、債権額に応じた按分弁済を受けることになりますが、微々たる額の配当しか受けられないケースが多いのが破産手続の実情です。
破産債権と財団債権は、政策的財団債権を除いて債権の発生原因によって区別されます。破産手続開始前の原因に基づいて発生した債権は破産債権、破産手続に関連して発生した債権は財団債権に分類されます。
破産債権の優先順位
破産債権の中にも優先順位があります。破産債権の優先順位は、次のとおりです(破産法194条1項)。
破産財団が破産債権を弁済するのに足りないときには、優先順位の高いものから順に弁済されます。
それぞれの債権の特徴や具体例を見ていきましょう。
1. 優先的破産債権
優先的破産債権とは、破産債権の中で最も優先的に配当を受けられる債権のことです。
優先的破産債権の具体例としては、財団債権に含まれない公租公課や労働債権が挙げられます。優先的破産債権の中でも優先順位が決められており、公租公課は労働債権よりも優先されます。
2. 一般的破産債権
一般の破産債権は、優先的破産債権に次いで配当される債権です。優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権に含まれない債権は、すべて一般の破産債権です。
一般の破産債権の具体例としては、銀行からの借入金や取引先の買掛金などが挙げられます。
一般の破産債権には優先順位がありません。そのため、配当金が一般の破産債権すべてを弁済するのに足りないときには、債権額に応じて配当が行われます(破産法194条2項)。
(配当の順位等)
第百九十四条
2 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
引用元 e-Gov法令検索|破産法
3. 劣後的破産債権
劣後的破産債権は、優先的破産債権と一般の破産債権を弁済しても余りがあるときに配当を受けられる債権です。
劣後的破産債権の具体例としては、破産手続開始後の利息、税金の延滞税など、破産手続の開始によって支払えなくなった債権に付随して発生する債権が挙げられます。
多くの破産手続では、破産財団が不十分で劣後的破産債権の配当まで行われるケースはほとんどありません。
4. 約定劣後破産債権
約定劣後破産債権とは、破産手続開始前に、破産債権者と破産者との間で、配当の順位が劣後的破産債権よりも下になる旨の合意がされた債権のことです(破産法99条2項)。
実務上、約定劣後破産債権の合意がされるケースはほとんどありません。また、約定劣後破産債権にまで配当が余ることも極めて少ないでしょう。
(劣後的破産債権等)
第九十九条
2 破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
引用元 e-Gov法令検索|破産法
財団債権とは?優先順位や弁済方法などをわかりやすく解説

債権者の破産者に対する債権(財産上の請求権)は、破産債権と財団債権に分けられます。財団債権は、破産手続によらずに随時弁済を受けられる債権です。破産手続においては、債権の優先順位や弁済方法を理解していなければ、弁済の見込みや時期なども把握できません。
今回は、財団債権とは何かを理解するために、財団債権の具体例や優先順位、弁済方法、破産債権との違いなどをわかりやすく解説します。破産手続における債権の分類について理解を深めるのにご活用ください。
財団債権とは破産手続によらず随時弁済を受けられる債権
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです(破産法2条7項)。
財団債権以外の債権(破産債権)は、破産手続の配当で債権額に応じて弁済されます。財団債権は、配当手続きを待たず破産債権に優先して弁済を受けられます。破産債権が弁済されるのは、財団債権を弁済しても余りがある場合だけです。
財団債権に分類される債権には複数の種類があり、それぞれに優先順位も存在します。ここでは、財団債権の具体例、財団債権の優先順位、弁済方法を解説します。
それぞれ順に解説いたします。
財団債権の2つの具体例

財団債権は、法的性質によって次の2つに分けられます。
- 本来的財団債権
- 政策的財団債権
本来、財団債権が破産債権よりも優先されるのは、破産手続を進めるのに必要不可欠な費用であるためです。この本来の意味での財団債権としての性質を持つ債権を、本来的財団債権と言います。
政策的財団債権は、本来は破産債権に分類される性質の債権を政策的な配慮から財団債権とされたものです。たとえば、破産者の使用人の給料は、破産手続開始前に発生しているもので破産手続を進めるのに必要な費用とは言えませんが、労働者保護という政策的な配慮から財団債権とされています(破産法149条1項)。
本来的財団債権は破産手続きに必要不可欠な費用の債権
本来的財団債権の具体例は、次のとおりです。
破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破産法148条1項1号)
破産手続の申立費用、債権者集会開催にかかる費用など
破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権(同項2号)
破産管財人の報酬など
破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(同項4号)
破産管財人が業務のために第三者と契約した際の相手方の債権など
事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(同項5号)
破産手続開始後に、第三者が義務なく破産財団に属する建物の修繕をした際の修理費用など
委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(同項6号)
破産手続開始によって委任契約が終了した後に、受任者が破産管財人に事務を引き継ぐ前に行った事務処理の費用など
破産法第53条第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権(破産法148条7号)
破産手続開始時に未履行の売買契約について、破産管財人が商品を受け取った場合における相手方の代金請求権など
破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れがあった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権(同項8号)
破産手続の開始から雇用契約終了までの給料債権など
政策的財団債権は一部の公租公課や労働債権
政策的財団債権の具体例は、次のとおりです。
- 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの(破産法148条1項3号)
- 破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権(同法149条1項)
- 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権のうち、退職前3月間の給料の総額に相当する額(同条2項)
公租公課や労働債権は、破産手続に必要な費用ではありませんが、租税徴収や労働者保護という政策的配慮から財団債権に分類されています。
財団債権の優先順位
破産財団の状況によっては、財団債権をすべて弁済できないケースもあります。破産財団の財産がすべての財団債権を弁済するのに足りないときは、次の優先順位で弁済されます(破産法152条)。
それぞれについて、具体的な内容と優先して弁済される理由を解説します。
1. 破産管財人への報酬
破産管財人への報酬は、何よりも優先して弁済を受けられます。
破産管財人の報酬は、破産財団の一部と引継予納金で構成されます。破産財団の財産が確保されるのは、破産管財人の換価業務の結果によるものです。破産財団の規模を大きくするには、その分だけ破産管財人の業務も多くなります。
破産管財人への報酬が優先されるのは、破産財団の規模に応じた報酬を保障することで、破産管財人が安心して破産手続を進められるためと言えるでしょう。
2. 債権者申立て又は第三者予納の予納金補填
法人の破産手続は、破産者だけでなく債権者による申立ても可能です。債権者が破産申立てをしたときには、破産者ではなく債権者が予納金を納付します。
破産財団から破産管財人への報酬を支払っても余剰があるときには、他の財団債権に優先して債権者の支払った予納金が返還されます。ただし、債権者申立ての場合、破産管財人の業務に債務者が協力することは期待できず、財産の調査や換価処分がスムーズに行えないケースもあるでしょう。そのため、債権者の予納金を返還するのに十分な破産財団を形成できないことも少なくありません。
3. 裁判の費用や管理・換価・配当費用の請求権
破産手続を進行するためには、申立費用や債権者集会を開催するための費用、破産手続開始決定の公告費用など、さまざまな費用がかかります(破産法148条1項1号・2号)。
破産手続の進行に必要な費用を確保しなければ手続きを進行できないため、これらの費用は「その他の財団債権」よりも優先して支払われます。
4. その他の財団債権
先に挙げた3つの項目に含まれない財団債権は、財団債権の中では優先順位が一番下となります。
政策的財団債権に当たる公租公課や労働債権は、その他の財団債権です。破産財団が同順位の財団債権を弁済するのに足りないときには、債権額に応じて弁済されます(破産法152条1項)。
財団債権の弁済方法は随時全額の支払いを受けられる
財産債権の弁済は、破産債権に優先して随時全額が支払われます(破産法151条)。財団債権の債権者は、破産開始決定後、破産管財人に財団債権を有する旨とその内容を申し出ることで、弁済を受けられます。
ただし、財団債権であっても、全額の弁済が保障されているわけではありません。破産財団が財団債権すべてを弁済できないときには、優先順位に従って弁済されます。優先順位が同順位の財団債権があるときには、債権額に応じて按分した額が弁済されます。
破産管財人が財団債権を承認するに際しては、裁判所の許可が必要です(破産法78条2項13号)。ただし、財団債権の額が100万円以下のときには裁判所の許可は不要となっており(破産法規則25条)、申し出があった債権について、管財人口座から随時弁済が行われます。
(財団債権の取扱い)
第百五十一条 財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。
引用元 e-Gov法令検索|破産法
財団債権と破産債権の違いは?
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、財団債権に該当しない債権のことです(破産法2条5項)。
たとえば、銀行からの借入金や、取引先の買掛金、外注費、財団債権に属しない労働債権など、会社を経営するうえで発生する債権は、ほとんどが破産債権です。
破産債権は、財団債権とは異なり、配当手続きを経なければ弁済を受けることができません。配当では、債権額に応じた按分弁済を受けることになりますが、微々たる額の配当しか受けられないケースが多いのが破産手続の実情です。
破産債権と財団債権は、政策的財団債権を除いて債権の発生原因によって区別されます。破産手続開始前の原因に基づいて発生した債権は破産債権、破産手続に関連して発生した債権は財団債権に分類されます。
破産債権の優先順位
破産債権の中にも優先順位があります。破産債権の優先順位は、次のとおりです(破産法194条1項)。
破産財団が破産債権を弁済するのに足りないときには、優先順位の高いものから順に弁済されます。
それぞれの債権の特徴や具体例を見ていきましょう。
1. 優先的破産債権
優先的破産債権とは、破産債権の中で最も優先的に配当を受けられる債権のことです。
優先的破産債権の具体例としては、財団債権に含まれない公租公課や労働債権が挙げられます。優先的破産債権の中でも優先順位が決められており、公租公課は労働債権よりも優先されます。
2. 一般的破産債権
一般の破産債権は、優先的破産債権に次いで配当される債権です。優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権に含まれない債権は、すべて一般の破産債権です。
一般の破産債権の具体例としては、銀行からの借入金や取引先の買掛金などが挙げられます。
一般の破産債権には優先順位がありません。そのため、配当金が一般の破産債権すべてを弁済するのに足りないときには、債権額に応じて配当が行われます(破産法194条2項)。
(配当の順位等)
第百九十四条
2 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
引用元 e-Gov法令検索|破産法
3. 劣後的破産債権
劣後的破産債権は、優先的破産債権と一般の破産債権を弁済しても余りがあるときに配当を受けられる債権です。
劣後的破産債権の具体例としては、破産手続開始後の利息、税金の延滞税など、破産手続の開始によって支払えなくなった債権に付随して発生する債権が挙げられます。
多くの破産手続では、破産財団が不十分で劣後的破産債権の配当まで行われるケースはほとんどありません。
4. 約定劣後破産債権
約定劣後破産債権とは、破産手続開始前に、破産債権者と破産者との間で、配当の順位が劣後的破産債権よりも下になる旨の合意がされた債権のことです(破産法99条2項)。
実務上、約定劣後破産債権の合意がされるケースはほとんどありません。また、約定劣後破産債権にまで配当が余ることも極めて少ないでしょう。
(劣後的破産債権等)
第九十九条
2 破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
引用元 e-Gov法令検索|破産法