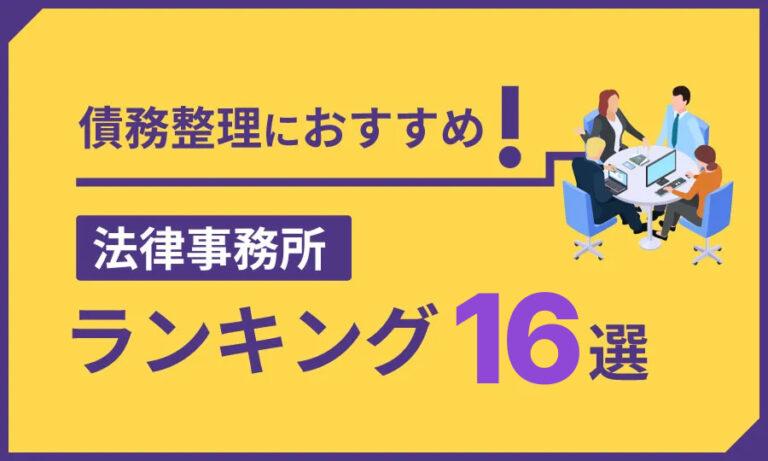準自己破産とは?必要な要件・費用について解説

自己破産という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、準自己破産という言葉を聞いたことがある方は多くないかもしれません。準自己破産は法人について行われる破産手続きのため、会社を経営している方にとっては知っておく必要があります。
この記事では、準自己破産をするために必要な要件や費用、準自己破産手続きの具体的な流れなどについて詳しく解説します。準自己破産の手続きを知っておきたい方は、最後までお読みください。
目次
準自己破産とは取締役などが申し立てる破産手続き
通常の自己破産は、法人自身または法人の債権者が申し立てることができます。一方、準自己破産とは、それ以外の者が自己破産の申し立てを行うことであり、破産法19条1項に規定されています。
以下では、準自己破産の申し立てができる人物、要件、手続きの流れを具体的に解説します。
それぞれ順に解説いたします。
準自己破産の申し立てができる人物
破産法19条1項では、以下のとおり法人の形態ごとに準自己破産の申し立てができる者を定めています。なお、以下の者以外に加えて清算人も準自己破産の申し立てが可能です。
- 一般社団法人または一般財団法人:理事
- 株式会社または相互会社:取締役
- 合名会社、合資会社または合同会社:業務を執行する社員
準自己破産の申し立てには疎明が必要
準自己破産を申し立てるためには、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないとされています(破産法19条3項)。通常の自己破産では求められませんが、準自己破産では必須であるため注意が必要です。
疎明とは
「疎明」とは、裁判官に対し、その事実があることを確信させるまでは必要ないものの、一応確からしいといえるまでの心証を抱かせることをいいいます。疎明資料を提出して裁判官に説明する必要があります。
破産手続開始の原因となる事実とは
準自己破産の申し立ての疎明要件である破産手続開始の原因となる事実とは、「支払不能」または「債務超過」に関する事実です。
「支払不能」とは、支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態です。「債務超過」とは、財産をもって債務を完済できない状態です。
準自己破産手続きの具体的な流れを解説

準自己破産手続きを行うためには、さまざな手続きを踏む必要があります。以下では、準自己破産の申し立てを行った後の具体的な手続きの流れを解説します。
破産手続開始の申し立て
準自己破産の申し立てを行う場合も、通常の自己破産の申し立てと同様、破産手続開始の申し立てを行う必要があります。申し立てに必要な書類は以下のとおりです。準自己破産の場合、破産手続開始の原因となる事実を疎明する資料の提出が必要です。なお、準自己破産の申し立てを弁護士に依頼する場合、これらに加えて委任状の提出も必要です。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 財産目録
- 破産手続開始の原因となる事実を疎明する資料
審尋
準自己破産の申し立てをすると、裁判所から審尋と呼ばれる質問を受けます。会社の状況や、破産手続開始の原因となる事実を中心に質問がされますので、あらかじめ準備しておきましょう。
破産手続開始決定
準自己破産の要件を満たしている場合、裁判所は破産手続開始の決定をするとともに、破産管財人を選任します。破産管財人は主に弁護士が選任され、法人の財産を換価処分して債権者に配当するなどの業務を行う者です。
法人財産の換価処分
破産手続開始の決定がなされると、法人の財産は破産財団と呼ばれ、すべての管理処分権は破産管財人に移ることになります。破産管財人は、法人の財産を換価処分し、債権者への配当に充てるための原資を作ります。
債権者集会
破産管財人は、破産手続開始の決定から3か月程度が経過したくらいに債権者集会を開いて法人の財産の換価処分の状況を報告します。
換価処分がすべて終了した後、破産管財人は債権者に配当を行います。
破産手続終結決定または破産手続廃止決定
債権者に対する配当が完了した後、裁判所は破産手続の終結を決定します。裁判所は、主文と理由を公告します。
一方、法人の財産で破産手続の費用が捻出できず債権者に対する配当ができないときは、裁判所は破産手続の廃止を決定します。
準自己破産の具体的な費用相場を解説
準自己破産の申し立てを行うためには、裁判所へ予納金を納める必要があります。また、申し立てについて弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用と予納金の具体的な費用相場について解説します。
それぞれ順に解説いたします。
準自己破産の弁護士費用相場は50〜100万円
準自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合の費用相場は50~100万円です。通常の管財事件であれば70万円前後が一般的な相場ですが、少額管財事件であれば20万円程度で収まる場合があります。もっとも、準自己破産の場合、取締役間で争いがあるなど複雑な事件が多いため、通常管財事件として扱われることが多いでしょう。なお、少額管財事件とするためには、弁護士へ依頼することが必須です。
裁判所への予納金は規模にもよるが70万円から
準自己破産の申し立てを行うためには、裁判所へ予納金を支払う必要があります。予納金とは破産手続きを進めるために必要となる費用であり、予納金を支払わないと、破産手続が開始されず却下されてしまうため注意が必要です。
予納金の内訳は以下のとおりです。
- 印紙代:破産手続開始申立書に貼付する必要があります。費用は1,000~1,500円程度です。
- 官報掲載料:破産手続が開始されると、政府の機関紙である官報に掲載されます。そのための費用として10,000~19,000円程度の費用がかかります。
- 郵券代:債権者や本人に書類を郵送するために3,000~5,000円分の郵便切手を予納する必要があります。
- 引継予納金:管財事件の場合、破産管財人に報酬を支払う必要があります。事案の複雑さによって報酬は異なりますが、通常管財事件であれば50万円から100万円程度の費用を予納する必要があります。
準自己破産をした方がいい具体的な3つのケース

通常の自己破産ではなく、準自己破産を申し立てたほうがいいケースがあります。以下では、具体的なケースを3つ紹介した上で、それぞれのケースについて解説します。同様のケースに直面している方は、準自己破産の申し立てを検討してみてください。
それぞれ順に解説いたします。
社長が逃げてしまい新社長を選任できない
社長が逃亡し行方がわからないような場合において、会社が破産を申し立てるためには、新たな代表取締役を取締役会で選任する必要があります。しかしながら適任の代表取締役がいなかったり、破産をする会社の代表取締役になっても意味がないという理由で、新たな代表取締役が選任できない事態に陥る場合があります。
このような場合、新たな代表取締役を選任せずとも、準自己破産を申し立てることによって破産手続を進めることが可能です。ただし、代表取締役が不在のままなので、破産裁判所に対し特別代理人選任の申し立てを行う必要があります。
破産に反対する役員がいて取締役会の同意が取れない
会社本人が自己破産を申し立てるためには、取締役会の承認を得る必要があります。取締役会の決議は、原則として議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって決します。破産に反対する取締役が過半数に達した場合、取締役会の承認を得ることができず、自己破産の申し立てができません。
このような場合、個々の取締役が準自己破産の申し立てができます。準自己破産を申し立てる際、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があります。取締役会の同意が取れない理由を詳細に記載する必要があるでしょう。
ステークホルダーの利益になる場合
会社が債務超過にあるような場合、破産申し立てをし、債務を免責してもらったほうがステークホルダーの利益になる場合があります。取締役がそのように考えた場合、取締役会で破産の申し立てを反対されたとしても、取締役単独で準自己破産の申し立てが可能です。
準自己破産のデメリットは難しさと費用負担
準自己破産は、通常の自己破産と比べてデメリットがあります。以下では、準自己破産の主なデメリットを2つ挙げて解説します。デメリットを理解した上で準自己破産をするか検討してください。
それぞれのデメリットについて順に解説いたします。
破産原因の疎明責任が必要で要件が厳しい
準自己破産の申し立ての際、通常の自己破産で提出する書類のほか、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があります。法人が支払不能または債務超過の状態であることを示す資料をそろえて裁判官に説明しなければなりませんので、難しい面があります。
費用を申し立て者が負担しなければならない
通常の自己破産を申し立てる場合、申し立てるのは法人であり、法人が予納金などの費用を支払います。しかし、準自己破産は取締役や理事が申し立てるため、法人ではなく申し立てた者が費用を支払わなければなりません。予納金で70万円以上、弁護士に依頼するとこれに加えて弁護士費用が50~100万円程度かかりますので、かなりの出費となります。
準自己破産に関するよくある質問
準自己破産は通常の自己破産の申し立てに比べて異なる手続きがあり、不明な点を持っている方もいると思います。以下では準自己破産に関するよくある質問を2つ挙げて回答します。同じような疑問を持っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
特別代理人を立てる必要があるケースを教えてください
会社の代表取締役が行方不明や死亡等で不在となった場合において、自己破産の申し立てをしたい場合、まずは取締役会で新たな代表取締役を選任します。しかし、新たな代表取締役を立てることが困難である場合、取締役個人が準自己破産を申し立てることになります。その場合、代表取締役が不在のままですので、破産裁判所に対し特別代理人を選任する必要があります。
取締役が勝手に準自己破産を申し立てました。破産を阻止できるか教えてください
取締役会で破産の承認決議が得られなくても、取締役個人が準自己破産を申し立てることは可能です。もっとも、破産法30条2号によれば、「不当な目的」で破産はできません。この不当な目的とは、債権者の権利が著しく害されるような場合です。会社側としては、取締役が不当な目的で準自己破産を申し立てたことを裁判所に対し説明する必要があるでしょう。
まとめ
法人の破産を申し立てたいが、会社が申立人として自己破産の申し立てができない事情がある場合、準自己破産の申し立てができます。
債務超過で自己破産を申し立てたほうが望ましいにもかかわらず取締役会で破産の承認決議が得られないような場合、準自己破産を検討する必要があります。
もっとも、準自己破産を申し立てるためには、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
準自己破産とは?必要な要件・費用について解説

自己破産という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、準自己破産という言葉を聞いたことがある方は多くないかもしれません。準自己破産は法人について行われる破産手続きのため、会社を経営している方にとっては知っておく必要があります。
この記事では、準自己破産をするために必要な要件や費用、準自己破産手続きの具体的な流れなどについて詳しく解説します。準自己破産の手続きを知っておきたい方は、最後までお読みください。
目次
準自己破産とは取締役などが申し立てる破産手続き
通常の自己破産は、法人自身または法人の債権者が申し立てることができます。一方、準自己破産とは、それ以外の者が自己破産の申し立てを行うことであり、破産法19条1項に規定されています。
以下では、準自己破産の申し立てができる人物、要件、手続きの流れを具体的に解説します。
それぞれ順に解説いたします。
準自己破産の申し立てができる人物
破産法19条1項では、以下のとおり法人の形態ごとに準自己破産の申し立てができる者を定めています。なお、以下の者以外に加えて清算人も準自己破産の申し立てが可能です。
- 一般社団法人または一般財団法人:理事
- 株式会社または相互会社:取締役
- 合名会社、合資会社または合同会社:業務を執行する社員
準自己破産の申し立てには疎明が必要
準自己破産を申し立てるためには、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないとされています(破産法19条3項)。通常の自己破産では求められませんが、準自己破産では必須であるため注意が必要です。
疎明とは
「疎明」とは、裁判官に対し、その事実があることを確信させるまでは必要ないものの、一応確からしいといえるまでの心証を抱かせることをいいいます。疎明資料を提出して裁判官に説明する必要があります。
破産手続開始の原因となる事実とは
準自己破産の申し立ての疎明要件である破産手続開始の原因となる事実とは、「支払不能」または「債務超過」に関する事実です。
「支払不能」とは、支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態です。「債務超過」とは、財産をもって債務を完済できない状態です。
準自己破産手続きの具体的な流れを解説

準自己破産手続きを行うためには、さまざな手続きを踏む必要があります。以下では、準自己破産の申し立てを行った後の具体的な手続きの流れを解説します。
破産手続開始の申し立て
準自己破産の申し立てを行う場合も、通常の自己破産の申し立てと同様、破産手続開始の申し立てを行う必要があります。申し立てに必要な書類は以下のとおりです。準自己破産の場合、破産手続開始の原因となる事実を疎明する資料の提出が必要です。なお、準自己破産の申し立てを弁護士に依頼する場合、これらに加えて委任状の提出も必要です。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 財産目録
- 破産手続開始の原因となる事実を疎明する資料
審尋
準自己破産の申し立てをすると、裁判所から審尋と呼ばれる質問を受けます。会社の状況や、破産手続開始の原因となる事実を中心に質問がされますので、あらかじめ準備しておきましょう。
破産手続開始決定
準自己破産の要件を満たしている場合、裁判所は破産手続開始の決定をするとともに、破産管財人を選任します。破産管財人は主に弁護士が選任され、法人の財産を換価処分して債権者に配当するなどの業務を行う者です。
法人財産の換価処分
破産手続開始の決定がなされると、法人の財産は破産財団と呼ばれ、すべての管理処分権は破産管財人に移ることになります。破産管財人は、法人の財産を換価処分し、債権者への配当に充てるための原資を作ります。
債権者集会
破産管財人は、破産手続開始の決定から3か月程度が経過したくらいに債権者集会を開いて法人の財産の換価処分の状況を報告します。
換価処分がすべて終了した後、破産管財人は債権者に配当を行います。
破産手続終結決定または破産手続廃止決定
債権者に対する配当が完了した後、裁判所は破産手続の終結を決定します。裁判所は、主文と理由を公告します。
一方、法人の財産で破産手続の費用が捻出できず債権者に対する配当ができないときは、裁判所は破産手続の廃止を決定します。
準自己破産の具体的な費用相場を解説
準自己破産の申し立てを行うためには、裁判所へ予納金を納める必要があります。また、申し立てについて弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用と予納金の具体的な費用相場について解説します。
それぞれ順に解説いたします。
準自己破産の弁護士費用相場は50〜100万円
準自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合の費用相場は50~100万円です。通常の管財事件であれば70万円前後が一般的な相場ですが、少額管財事件であれば20万円程度で収まる場合があります。もっとも、準自己破産の場合、取締役間で争いがあるなど複雑な事件が多いため、通常管財事件として扱われることが多いでしょう。なお、少額管財事件とするためには、弁護士へ依頼することが必須です。
裁判所への予納金は規模にもよるが70万円から
準自己破産の申し立てを行うためには、裁判所へ予納金を支払う必要があります。予納金とは破産手続きを進めるために必要となる費用であり、予納金を支払わないと、破産手続が開始されず却下されてしまうため注意が必要です。
予納金の内訳は以下のとおりです。
- 印紙代:破産手続開始申立書に貼付する必要があります。費用は1,000~1,500円程度です。
- 官報掲載料:破産手続が開始されると、政府の機関紙である官報に掲載されます。そのための費用として10,000~19,000円程度の費用がかかります。
- 郵券代:債権者や本人に書類を郵送するために3,000~5,000円分の郵便切手を予納する必要があります。
- 引継予納金:管財事件の場合、破産管財人に報酬を支払う必要があります。事案の複雑さによって報酬は異なりますが、通常管財事件であれば50万円から100万円程度の費用を予納する必要があります。
準自己破産をした方がいい具体的な3つのケース

通常の自己破産ではなく、準自己破産を申し立てたほうがいいケースがあります。以下では、具体的なケースを3つ紹介した上で、それぞれのケースについて解説します。同様のケースに直面している方は、準自己破産の申し立てを検討してみてください。
それぞれ順に解説いたします。
社長が逃げてしまい新社長を選任できない
社長が逃亡し行方がわからないような場合において、会社が破産を申し立てるためには、新たな代表取締役を取締役会で選任する必要があります。しかしながら適任の代表取締役がいなかったり、破産をする会社の代表取締役になっても意味がないという理由で、新たな代表取締役が選任できない事態に陥る場合があります。
このような場合、新たな代表取締役を選任せずとも、準自己破産を申し立てることによって破産手続を進めることが可能です。ただし、代表取締役が不在のままなので、破産裁判所に対し特別代理人選任の申し立てを行う必要があります。
破産に反対する役員がいて取締役会の同意が取れない
会社本人が自己破産を申し立てるためには、取締役会の承認を得る必要があります。取締役会の決議は、原則として議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって決します。破産に反対する取締役が過半数に達した場合、取締役会の承認を得ることができず、自己破産の申し立てができません。
このような場合、個々の取締役が準自己破産の申し立てができます。準自己破産を申し立てる際、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があります。取締役会の同意が取れない理由を詳細に記載する必要があるでしょう。
ステークホルダーの利益になる場合
会社が債務超過にあるような場合、破産申し立てをし、債務を免責してもらったほうがステークホルダーの利益になる場合があります。取締役がそのように考えた場合、取締役会で破産の申し立てを反対されたとしても、取締役単独で準自己破産の申し立てが可能です。
準自己破産のデメリットは難しさと費用負担
準自己破産は、通常の自己破産と比べてデメリットがあります。以下では、準自己破産の主なデメリットを2つ挙げて解説します。デメリットを理解した上で準自己破産をするか検討してください。
それぞれのデメリットについて順に解説いたします。
破産原因の疎明責任が必要で要件が厳しい
準自己破産の申し立ての際、通常の自己破産で提出する書類のほか、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があります。法人が支払不能または債務超過の状態であることを示す資料をそろえて裁判官に説明しなければなりませんので、難しい面があります。
費用を申し立て者が負担しなければならない
通常の自己破産を申し立てる場合、申し立てるのは法人であり、法人が予納金などの費用を支払います。しかし、準自己破産は取締役や理事が申し立てるため、法人ではなく申し立てた者が費用を支払わなければなりません。予納金で70万円以上、弁護士に依頼するとこれに加えて弁護士費用が50~100万円程度かかりますので、かなりの出費となります。
準自己破産に関するよくある質問
準自己破産は通常の自己破産の申し立てに比べて異なる手続きがあり、不明な点を持っている方もいると思います。以下では準自己破産に関するよくある質問を2つ挙げて回答します。同じような疑問を持っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
特別代理人を立てる必要があるケースを教えてください
会社の代表取締役が行方不明や死亡等で不在となった場合において、自己破産の申し立てをしたい場合、まずは取締役会で新たな代表取締役を選任します。しかし、新たな代表取締役を立てることが困難である場合、取締役個人が準自己破産を申し立てることになります。その場合、代表取締役が不在のままですので、破産裁判所に対し特別代理人を選任する必要があります。
取締役が勝手に準自己破産を申し立てました。破産を阻止できるか教えてください
取締役会で破産の承認決議が得られなくても、取締役個人が準自己破産を申し立てることは可能です。もっとも、破産法30条2号によれば、「不当な目的」で破産はできません。この不当な目的とは、債権者の権利が著しく害されるような場合です。会社側としては、取締役が不当な目的で準自己破産を申し立てたことを裁判所に対し説明する必要があるでしょう。
まとめ
法人の破産を申し立てたいが、会社が申立人として自己破産の申し立てができない事情がある場合、準自己破産の申し立てができます。
債務超過で自己破産を申し立てたほうが望ましいにもかかわらず取締役会で破産の承認決議が得られないような場合、準自己破産を検討する必要があります。
もっとも、準自己破産を申し立てるためには、破産手続開始の原因となる事実を疎明する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。