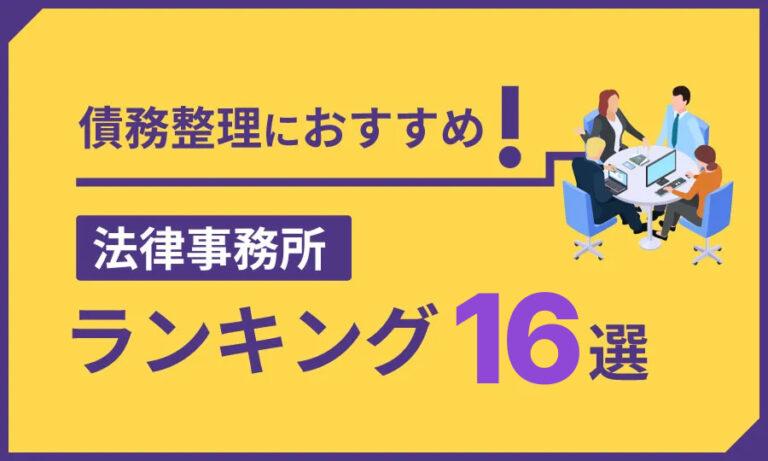私的整理とは?法的整理との違いやメリット・デメリットを解説

私的整理とは、経営危機に陥った企業が債務を圧縮し、事業の立て直しを図るために有効な手段のひとつです。債権者と直接交渉し、金銭債務の支払い猶予や返済額の減免等を図る手続きです。
債務超過に陥った企業は会社更生や民事再生といった法的整理を選択することも考えられますが、手続きにかかる手間や時間、費用の負担が大きくなります。
それに対して、私的整理では時間や費用の負担を抑えつつ、柔軟な解決を図ることが可能です。企業イメージの低下を防止し、取引先との信頼関係を維持しやすいというメリットもあります。
したがって、企業の再建を図るためには、まず私的整理を検討するとよいでしょう。この記事では、私的整理の概要や法的整理との違い、私的整理のメリットおよびデメリットについて解説します。
私的整理とは法的手続きによらない債務整理
私的整理とは、裁判所で行われる法的手続きによらない、企業向けの債務整理のことです。当事者間の合意に基づいて債務を整理する手続きであることから、私的整理と呼ばれています。
まずは、私的整理と法的整理の違いや私的整理の概要について詳しく解説します。
私的整理と法的整理の違いは?
私的整理が当事者間の合意に基づき債務の整理をする手続きであるのに対して、法的整理は裁判所に申し立てをして、法律で定められた手続きを経て債務を整理する手続きであるという違いがあります。
法的整理に該当する具体的な手続きには、以下の4種類があります。
- 破産
- 特別清算
- 会社更生
- 民事再生
破産と特別清算は清算型の倒産手続きとも呼ばれており、手続きが終了すると企業の法人格は消滅します。
会社更生と民事再生は再建型の倒産手続きとも呼ばれているものであり、債務の減免によって事業を再建を図り、企業の法人格を存続させるための手続きです。
私的整理も、事業の再建のために行われることもあれば、廃業に伴う清算のために行われることもあります。しかし、一般的には事業の再建を図るために私的整理が行われるケースが多いです。
再建型の私的整理と法的整理には、法人格の存続を前提として事業の再建を図るという共通点がありますが、以下のような違いもあります。
| 私的整理 | 法的整理 | |
|---|---|---|
| 利用できる要件 | 明確には存在しない | 法律で定められている |
| 債務を圧縮できる程度 | 債権者の意向次第で大幅な圧縮は難しいこともある | 大幅な圧縮が可能 |
| 債権者の合意 | 必要 | 民事再生では多数債権者の同意が必要 |
| 対象となる債権者 | 自由に選べる | 全債権者を対象とする必要がある |
| 手続き費用 | 特になし | 200万円~数千万円 (手続きの種類や債務総額によって変動する) |
| 手続き期間 | 3ヶ月~数年程度 | 民事再生では6ヶ月程度 会社更生では1~3年程度 |
| 透明性・公平性 | 不透明・不公平との印象を持たれることがある | 裁判所の関与により透明性・公平性が担保される |
| 公になるリスク | 裁判所を通さないため低い | 官報に掲載されるため高い |
それぞれについて順に解説いたします。
私的整理ができる要件は明確に存在しない
私的整理は法律で定められた手続きではないので、利用するための明確な要件は存在しません。企業の規模や債権者数、債務額にかかわらず、利用できる可能性があります。
ただし、私的整理を成功させるためには、手続きの対象とした債権者全員との合意が得られることが絶対的な条件です。合意することが難しいと見込まれる場合には、法的整理の検討が必要です。
債権者数が多い場合や、債務額が大きい場合は、各債権者から合意を得るために多大な手間を要したり、債務の減免に難色を示す債権者も少なくないでしょう。場合によっては、私的整理を進めることは難しいかもしれません。
また、取引先に対して債務の減免を求めると取引停止となり、事業の継続に支障をきたすおそれが強いです。そのため、私的整理は融資先の金融機関のみを対象として行われるケースが多くなっています。
金融機関に対する債務を減免すれば事業の継続が可能であり、その金融機関との合意が見込まれるケースは、私的整理に向いているといえるでしょう。
破産の規模によるが中小企業は私的整理も検討しやすい
私的整理は、企業の規模を問わず利用できます。ただし、大企業の場合は債権者数が多く、各債権者との権利義務関係も複雑に絡み合っていることが多いものです。
このような場合でも私的整理は利用可能ですが、手続きにかかる手間や時間の負担が大きくなります。弁護士などの専門家に手続きを依頼すれば、費用の負担も大きくなるでしょう。
債権者数が多ければ多いほど、返済計画案に合意しない債権者が現れる可能性が高まることにも注意が必要です。手続きの対象とした全債権者と合意できなければ、私的整理は失敗に終わってしまいます。
それに対して、中小企業の場合は債権者数が比較的少ないケースが多いものです。手続きにかかる手間や時間の負担も、そこまで大きなものにはなりません。手続きは弁護士などの専門家に依頼するケースが多いですが、費用の負担も大企業のケースと比べれば軽いです。
そのため、一般的な傾向としてですが、中小企業は法的整理に踏み切る前に、私的整理も検討しやすいといえるでしょう。
私的整理の種類と手続きの具体的な流れ
ひと口に私的整理といっても、大きく分けて次の2種類の手続きがあります。
任意交渉による私的整理とは、各債権者と個別に直接交渉し、ルールに縛られない自由な交渉によって合意を目指す手続きです。
それに対して、準則型私的整理とは、第三者機関が策定したガイドラインなどに基づく一定のルールに従って各債権者との合意を目指す手続きです。
以下で、それぞれの手続きについて、具体的な流れを解説します。
任意交渉による私的整理

任意交渉による私的整理では、進め方に関する明確なルールはありません。そのため、適宜の方法で債権者との話し合いの場を持ち、債務者が希望する返済計画案を提示して交渉していくことも理論上は可能です。
しかし、債務者の希望を一方的に伝えるだけでは、債権者との合意を得ることは難しいでしょう。そのため、まずは債権者の理解が得られるような資料を作成することが重要となります。
具体的には、自社の経営課題を把握して、改善のための施策を検討することが必要です。その上で新たな事業計画を策定し、その計画を遂行するために必要な支払い猶予や債務の減免、返済スケジュールなどを策定していきます。
債権者との交渉に際しては、以上の内容を説得的に記載した資料を提供し、分かりやすく説明することがまず大切です。
ただし、充実した資料を作成するためには非常に専門的な知識や経験が要求されます。資料の作成に時間がかかると、その間に経営状況が悪化することもあるでしょう。そのため、私的整理をするためには、早い段階で弁護士などの専門家によるサポートを受けるのが得策です。
弁護士に私的整理を依頼すれば、まずは弁護士が各債権者に対して受任通知を送付し、私的整理の希望を伝えます。ほとんどの場合、この段階で支払いの催促が止まります。
そして、資料の作成も弁護士のサポートを受けてスムーズに行うことが可能です。充実した資料ができたら、弁護士が各債権者と交渉します。当事者双方が納得できる返済計画案で合意できたら、合意書を交わして交渉は終了です。
その後は、合意によって新たに取り決めた返済計画案に従って、債務の返済を進めていきます。
準則型私的整理
準則型私的整理にもさまざまな種類がありますが、ここでは代表的な3つの手続きをご紹介します。
それぞれについて、手続きの具体的な流れをみていきましょう。
事業再生ADR

事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者(特定認証紛争解決事業者)の仲介で債権者と債務者が交渉し、債務者である企業の事業再生を図る制度です。
「ADR」とは、「裁判外紛争解決手続」の略称であり、当事者間の法的な紛争について裁判手続以外で解決を図る手続きのことを指します。
「特定認証紛争解決事業者」とは、産業競争力強化法第47条第1項に基づき経済産業大臣の認定を受けた事業者のことです。この認定を受けた事業者として、一般社団法人事業再生実務家協会があります。
具体的な手続きとしては、まず、債務者が特定認証紛争解決事業者に対し、手続き利用申請を行います。利用申請に際しては、任意交渉による私的整理の場合と同様、事業計画や返済計画を記載した資料の準備が必要です。
申請が受理されると、特定認証紛争解決事業者と債務者との連名で、一時停止の通知を発出します。この通知が債権者に届くと、基本的に個別の債権回収行為が止まります。
その後は各債権者と個別に交渉するのではなく、債権者会議が開催されるのが特徴的です。債権者会議では、債務者から負債や資産の状況、事業再生計画案などの概要を説明し、質疑応答や意見交換が行われます。
最終的に債権者全員の同意が得られたら、私的整理の成立です。その後は、決議された事業再生計画案に従って、債務の返済を進めていきます。
中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生を支援するために、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき設置された、公正中立な公的機関です。中小企業の事業再生支援の一環として、中小企業再生支援協議会は私的整理のサポートも行っています。
手続きの流れとしては、まず、各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会の窓口に相談します。相談時には、負債や資産の状況、経営状況などが記載された資料を持参し、自社が置かれた状況を分かりやすく説明することが重要です。
中小企業再生支援協議会は、面談や提出資料の分析を通じて問題点を抽出し、問題解決に向けて適切なアドバイスを行います。融資先の金融機関と調整する必要があると判断した場合には、私的整理の手続きに入ります。
その前提として具体的な再生計画を策定する必要がありますが、この段階から中小企業再生支援協議会によるサポートを受けることが可能です。
再生計画の策定ができたら、中小企業再生支援協議会が金融機関等の債権者と債務者との間に入り、再生計画案への合意形成を目指します。全債権者との合意が得られたら、私的整理の成立です。
その後は合意した再生計画に従って債務を返済していきますが、中小企業再生支援協議会が定期的にフォローアップしてくれます。必要に応じて専門的なアドバイスが受けられるので、安心して事業の再建に取り組むことができるでしょう。
RCC企業再生スキーム

RCC企業再生スキームとは、株式会社整理回収機構(RCC)が行う私的整理の手続について、その内容や要件をまとめたもののことです。
RCCは株式会社ではありますが、法律や政府からの要請に基づき業務を行う、公的な使命を帯びた会社です。当初は金融機関の不良債権を整理・回収する株式会社として設立されましたが、その後、金融再生法の改正に伴い、企業再生にかかわる業務も担うようになりました。
手続きの流れとしては、まず、東京または大阪に設置されている相談室に相談します。RCCの専門部局である企業再生部において、企業再生に取り組むのが妥当であると判断された事案については、私的整理の手続きに入ります。
その後、速やかに第1回債権者集会が開催され、そこで債務者は事業や財務の状況、再生の可能性などを説明します。この債権者集会において、債務者およびRCCは個別の債権回収や担保権の実行などを阻止するために、各債権者と一時停止の合意形成を図ります。
一時停止が合意された後、債務者は再生計画案を策定し、RCCへ提出しなければなりません。再生計画案を提出すると第2回債権者集会が開催され、質疑応答や意見交換を経て、対象債権者による決議が行われます。対象債権者全員の同意が得られると、再生計画の成立です。その後は、再生計画に従って債務の返済を進めていきます。
RCC企業再生スキームでは、再生計画成立後も定期的に債権者集会が開催され、債務者はその際に再生計画の実行状況等を報告しなければなりません。
私的整理の4つのメリット

私的整理と法的整理を比べた場合、私的整理のメリットとして以下の4つが挙げられます。
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
世間に知られにくく信用低下が起こりにくい
私的整理には、手続きを行ったことが世間に知られにくく、信用低下が起こりにくいというメリットがあります。
事業を再生するためには、売掛先などの取引先や、買掛先などの一般債権者からの信用を保つことが重要です。世間に対する良好な企業イメージを損なうことも回避したいところでしょう。
私的整理の手続きは裁判所を通さないため、世間に公表されることがありません。そのため、企業イメージの著しい低下を回避できます。
また、手続きの対象とした債権者を除く関係者の債権には影響がないので、迷惑がかかりません。対象とする債権者を適切に選んで手続きを行えば、重要な取引先等からの信用を保ったまま、事業の再生を図ることが可能です。
その点、法的整理ではすべての債権者が手続きの対象となり、重要な取引先が有する債権も強制的に減免の対象となってしまいます。債務の圧縮に成功したとしても、重要な取引先を失ってしまうことも少なくありません。
さらに、特定調停以外の法的整理をすると、官報に企業名や行った手続きの種類などが掲載され、世間に公表されます。これにより、倒産した企業という認識が広まってしまい、企業イメージの低下を招くおそれが強いです。
したがって、事業を円滑に再生するためには、法的整理よりもまず私的整理を検討した方がよいでしょう。
当事者の合意に基づいて柔軟な解決を目指せる
私的整理には、当事者の合意に基づいて柔軟な解決を目指せるというメリットもあります。
私的整理では債務の減免に関する明確なルールはないので、当事者が合意すれば、債務の内容を自由に変更できます。
例えば、私的整理にあまり協力的ではない債権者への返済率は高めにし、協力的な債権者への返済率は低めにするなどして、全体的に遂行可能な再生計画を策定することも考えられるでしょう。
また、私的整理では手続きの対象とする債権者を自由に選べます。合意が見込めない債権者は除外して、合意が見込める債権だけを対象として手続きをすることも可能です。
それに対して、法的整理ではすべての債権者を手続きの対象とし、各債権者を平等に扱わなければなりません。
債務の変更内容も、法律の規定に従って画一的に決めなければならないため、柔軟な解決を目指すことは困難です。
順調に進めば解決までの時間が節約できる
私的整理には長い期間がかかることもありますが、順調に進めば短期間で手続きを終了できるので、解決までの時間を節約できるという点もメリットの1つです。
私的整理では、当事者が合意さえすれば手続きが終了します。企業の状況を示す資料の準備や再生計画案の策定、交渉などにある程度の期間は要しますが、早ければ3ヶ月程度で解決できることもあります。
その点、法的整理では裁判所に申し立てをして、法律で定められた手続きを踏む必要があることから、長い期間がかかることは避けられません。民事再生の手続きは概ね6ヶ月程度で終了しますが、会社更生の手続きは1~3年程度かかるのが一般的です。
速やかに事業を再生したい場合、解決までの時間を節約できる私的整理のメリットは大きいといえるでしょう。
予納金などの負担がなく費用を抑えられる
私的整理は裁判所を通さない手続きであるため、予納金などの負担がなく費用を抑えられるというメリットも挙げられます。
この点、法的整理では裁判所に予納金を納めなければなりません。具体的な予納金の額は企業の規模や債権者数、債務総額などによって異なりますが、一般的に法人の倒産手続きにおける予納金は高額となります。
民事再生では200万円~1200万円程度、会社更生では800万円~3000万円程度が目安です。
ただし、私的整理でも弁護士に手続きを依頼する場合は、弁護士費用がかかることには注意しましょう。
とはいえ、一般的に私的整理では法的整理よりも手続きの負担が軽いため、弁護士費用も低い傾向にあります。そのため、弁護士費用を考慮しても、私的整理の方が費用の負担は圧倒的に軽いことが多いです。
低コストで債務を圧縮し、事業の再生を図れるという点でも、私的整理のメリットは大きいといえるでしょう。
私的整理の2つのデメリット

私的整理には大きなメリットがありますが、以下のように2つのデメリットがあることにも注意が必要です。
それぞれのデメリットについて、詳しくみていきましょう。
債権者の同意が得られない場合がある
私的整理では、債権者の同意が得られない場合があるというデメリットがあります。債務者が策定した再生計画案に同意するかどうかは、債権者の意向次第です。
私的整理の手続きには法的な強制力がないため、債権者に同意を強制することはできません。同意が得られなければ、私的整理に失敗してしまいます。私的整理の交渉に一切応じない債権者もいますし、交渉には応じるものの、同意する前提として厳しい条件を提示してくる債権者もいます。
借り入れてから間もない場合や、長期間にわたって滞納を続けている場合などでは、同意のための条件が厳しくなることが多いです。同意が見込めない債権者は除外して私的整理を行うこともできますが、対象債権者が少なければ債務を圧縮できる幅も小さくなります。
思うように債務を圧縮できなければ、事業再生という目的を果たせなくなることもあるでしょう。主要債権者の同意が得られない場合など、私的整理では目的を果たすことが難しい場合には、法的整理を検討する必要があります。
手続きが不透明だと不信感を持たれる場合がある
私的整理では、手続きの内容が不透明になりがちであり、そのために一部の債権者などから不信感を持たれる場合があるということもデメリットとして挙げられます。
私的整理の手続きの進め方には明確なルールが存在しないため、各債権者と個別に交渉することも可能です。その場合、債権者から見れば再生計画の全体像が不透明となり、他の債権者よりも不利に扱われているのではないかという疑念を抱くことがあります。
このようにして債権者から不信感を持たれると、その債権者の同意を得ることが難しくなりがちです。同意を得られたとしても、取引の継続が難しくなることもあるでしょう。
ひいては、株主など債権者以外の利害関係者(ステークホルダー)からも不信感を持たれて、事業の再生に支障をきたすことになりかねません。
その点、法的整理では裁判所の手続きにおいて全債権者が平等に扱われ、高い透明性が確保されています。したがって、法的整理をすると、債権者から債務の減免という結果に不満を持たれることはあっても、手続きに不信感を持たれることはありません。
私的整理に関するガイドラインに沿って進めよう
私的整理における手続きの不透明さを回避するために、「私的整理に関するガイドライン」に沿って手続きを進めるという方法があります。
私的整理に関するガイドラインとは、公正かつ衡平な私的整理が円滑に成立するように、模範的なルールを定めたものです。
政府が平成13年に発表した緊急経済対策を受けて、経済団体連合会や全国銀行協会などで構成された私的整理に関するガイドライン研究会によって策定・公表されました。
ガイドラインに沿った私的整理では、原則として債権者会議が開催されます。そこで再生計画案の説明や質疑応答などが行われるため、手続きの透明性が確保されるという仕組みです。
参考:私的整理に関するガイドライン研究会|私的整理に関するガイドライン
ただし、私的整理に関するガイドラインは主に大企業を想定した内容となっており、中小企業は利用しにくいという問題点がありました。
そこで、令和4年3月には、政府が設置した中小企業の事業再生等に関する研究会により策定・公表されたのが「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」です。
こちらのガイドラインでも、「第三部 中小企業の事業再生等のための私的整理手続」という章で、透明性を確保した私的整理手続きに関する模範的なルールが示されています。
参考:中小企業の事業再生等に関する研究会|中小企業の事業再生等に関するガイドライン
大企業は私的整理に関するガイドラインを、中小企業は中小企業の事業再生等に関するガイドラインを活用した私的整理を検討するとよいでしょう。
いずれのガイドラインにも法的拘束力はありませんが、金融機関はガイドラインで示されたルールを尊重する傾向にあるので、債権者である金融機関の合意も得られやすくなるはずです。
私的整理に関するよくある質問
最後に、私的整理に関してよくある質問に回答します。
個人でも私的整理を行えますか?
本記事でご紹介した私的整理には明確なルールが存在しないため、個人でも私的整理を行うことも不可能ではありません。個人事業主として比較的規模の大きい事業を営んでいる場合は、私的整理を検討するのもよいでしょう。
ただし、個人が法的手続き以外で債務整理をする場合は、任意整理を行うのが一般的です。
任意整理とは、各債権者と個別に直接交渉を行い、合意によって債務の減免を求める手続きです。一般的には、今後の利息をカットしてもらい、残元金を3~5年の分割で返済していきます。
任意整理においても、合意するかどうかは債権者の意向に委ねられることに注意が必要です。債務者が自分で債権者と交渉すると厳しい条件を提示されることが多いですが、弁護士に任意整理を依頼すると有利な条件で合意が得られやすくなる傾向にあります。
私的整理とは?法的整理との違いやメリット・デメリットを解説

私的整理とは、経営危機に陥った企業が債務を圧縮し、事業の立て直しを図るために有効な手段のひとつです。債権者と直接交渉し、金銭債務の支払い猶予や返済額の減免等を図る手続きです。
債務超過に陥った企業は会社更生や民事再生といった法的整理を選択することも考えられますが、手続きにかかる手間や時間、費用の負担が大きくなります。
それに対して、私的整理では時間や費用の負担を抑えつつ、柔軟な解決を図ることが可能です。企業イメージの低下を防止し、取引先との信頼関係を維持しやすいというメリットもあります。
したがって、企業の再建を図るためには、まず私的整理を検討するとよいでしょう。この記事では、私的整理の概要や法的整理との違い、私的整理のメリットおよびデメリットについて解説します。
私的整理とは法的手続きによらない債務整理
私的整理とは、裁判所で行われる法的手続きによらない、企業向けの債務整理のことです。当事者間の合意に基づいて債務を整理する手続きであることから、私的整理と呼ばれています。
まずは、私的整理と法的整理の違いや私的整理の概要について詳しく解説します。
私的整理と法的整理の違いは?
私的整理が当事者間の合意に基づき債務の整理をする手続きであるのに対して、法的整理は裁判所に申し立てをして、法律で定められた手続きを経て債務を整理する手続きであるという違いがあります。
法的整理に該当する具体的な手続きには、以下の4種類があります。
- 破産
- 特別清算
- 会社更生
- 民事再生
破産と特別清算は清算型の倒産手続きとも呼ばれており、手続きが終了すると企業の法人格は消滅します。
会社更生と民事再生は再建型の倒産手続きとも呼ばれているものであり、債務の減免によって事業を再建を図り、企業の法人格を存続させるための手続きです。
私的整理も、事業の再建のために行われることもあれば、廃業に伴う清算のために行われることもあります。しかし、一般的には事業の再建を図るために私的整理が行われるケースが多いです。
再建型の私的整理と法的整理には、法人格の存続を前提として事業の再建を図るという共通点がありますが、以下のような違いもあります。
| 私的整理 | 法的整理 | |
|---|---|---|
| 利用できる要件 | 明確には存在しない | 法律で定められている |
| 債務を圧縮できる程度 | 債権者の意向次第で大幅な圧縮は難しいこともある | 大幅な圧縮が可能 |
| 債権者の合意 | 必要 | 民事再生では多数債権者の同意が必要 |
| 対象となる債権者 | 自由に選べる | 全債権者を対象とする必要がある |
| 手続き費用 | 特になし | 200万円~数千万円 (手続きの種類や債務総額によって変動する) |
| 手続き期間 | 3ヶ月~数年程度 | 民事再生では6ヶ月程度 会社更生では1~3年程度 |
| 透明性・公平性 | 不透明・不公平との印象を持たれることがある | 裁判所の関与により透明性・公平性が担保される |
| 公になるリスク | 裁判所を通さないため低い | 官報に掲載されるため高い |
それぞれについて順に解説いたします。
私的整理ができる要件は明確に存在しない
私的整理は法律で定められた手続きではないので、利用するための明確な要件は存在しません。企業の規模や債権者数、債務額にかかわらず、利用できる可能性があります。
ただし、私的整理を成功させるためには、手続きの対象とした債権者全員との合意が得られることが絶対的な条件です。合意することが難しいと見込まれる場合には、法的整理の検討が必要です。
債権者数が多い場合や、債務額が大きい場合は、各債権者から合意を得るために多大な手間を要したり、債務の減免に難色を示す債権者も少なくないでしょう。場合によっては、私的整理を進めることは難しいかもしれません。
また、取引先に対して債務の減免を求めると取引停止となり、事業の継続に支障をきたすおそれが強いです。そのため、私的整理は融資先の金融機関のみを対象として行われるケースが多くなっています。
金融機関に対する債務を減免すれば事業の継続が可能であり、その金融機関との合意が見込まれるケースは、私的整理に向いているといえるでしょう。
破産の規模によるが中小企業は私的整理も検討しやすい
私的整理は、企業の規模を問わず利用できます。ただし、大企業の場合は債権者数が多く、各債権者との権利義務関係も複雑に絡み合っていることが多いものです。
このような場合でも私的整理は利用可能ですが、手続きにかかる手間や時間の負担が大きくなります。弁護士などの専門家に手続きを依頼すれば、費用の負担も大きくなるでしょう。
債権者数が多ければ多いほど、返済計画案に合意しない債権者が現れる可能性が高まることにも注意が必要です。手続きの対象とした全債権者と合意できなければ、私的整理は失敗に終わってしまいます。
それに対して、中小企業の場合は債権者数が比較的少ないケースが多いものです。手続きにかかる手間や時間の負担も、そこまで大きなものにはなりません。手続きは弁護士などの専門家に依頼するケースが多いですが、費用の負担も大企業のケースと比べれば軽いです。
そのため、一般的な傾向としてですが、中小企業は法的整理に踏み切る前に、私的整理も検討しやすいといえるでしょう。
私的整理の種類と手続きの具体的な流れ
ひと口に私的整理といっても、大きく分けて次の2種類の手続きがあります。
任意交渉による私的整理とは、各債権者と個別に直接交渉し、ルールに縛られない自由な交渉によって合意を目指す手続きです。
それに対して、準則型私的整理とは、第三者機関が策定したガイドラインなどに基づく一定のルールに従って各債権者との合意を目指す手続きです。
以下で、それぞれの手続きについて、具体的な流れを解説します。
任意交渉による私的整理

任意交渉による私的整理では、進め方に関する明確なルールはありません。そのため、適宜の方法で債権者との話し合いの場を持ち、債務者が希望する返済計画案を提示して交渉していくことも理論上は可能です。
しかし、債務者の希望を一方的に伝えるだけでは、債権者との合意を得ることは難しいでしょう。そのため、まずは債権者の理解が得られるような資料を作成することが重要となります。
具体的には、自社の経営課題を把握して、改善のための施策を検討することが必要です。その上で新たな事業計画を策定し、その計画を遂行するために必要な支払い猶予や債務の減免、返済スケジュールなどを策定していきます。
債権者との交渉に際しては、以上の内容を説得的に記載した資料を提供し、分かりやすく説明することがまず大切です。
ただし、充実した資料を作成するためには非常に専門的な知識や経験が要求されます。資料の作成に時間がかかると、その間に経営状況が悪化することもあるでしょう。そのため、私的整理をするためには、早い段階で弁護士などの専門家によるサポートを受けるのが得策です。
弁護士に私的整理を依頼すれば、まずは弁護士が各債権者に対して受任通知を送付し、私的整理の希望を伝えます。ほとんどの場合、この段階で支払いの催促が止まります。
そして、資料の作成も弁護士のサポートを受けてスムーズに行うことが可能です。充実した資料ができたら、弁護士が各債権者と交渉します。当事者双方が納得できる返済計画案で合意できたら、合意書を交わして交渉は終了です。
その後は、合意によって新たに取り決めた返済計画案に従って、債務の返済を進めていきます。
準則型私的整理
準則型私的整理にもさまざまな種類がありますが、ここでは代表的な3つの手続きをご紹介します。
それぞれについて、手続きの具体的な流れをみていきましょう。
事業再生ADR

事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者(特定認証紛争解決事業者)の仲介で債権者と債務者が交渉し、債務者である企業の事業再生を図る制度です。
「ADR」とは、「裁判外紛争解決手続」の略称であり、当事者間の法的な紛争について裁判手続以外で解決を図る手続きのことを指します。
「特定認証紛争解決事業者」とは、産業競争力強化法第47条第1項に基づき経済産業大臣の認定を受けた事業者のことです。この認定を受けた事業者として、一般社団法人事業再生実務家協会があります。
具体的な手続きとしては、まず、債務者が特定認証紛争解決事業者に対し、手続き利用申請を行います。利用申請に際しては、任意交渉による私的整理の場合と同様、事業計画や返済計画を記載した資料の準備が必要です。
申請が受理されると、特定認証紛争解決事業者と債務者との連名で、一時停止の通知を発出します。この通知が債権者に届くと、基本的に個別の債権回収行為が止まります。
その後は各債権者と個別に交渉するのではなく、債権者会議が開催されるのが特徴的です。債権者会議では、債務者から負債や資産の状況、事業再生計画案などの概要を説明し、質疑応答や意見交換が行われます。
最終的に債権者全員の同意が得られたら、私的整理の成立です。その後は、決議された事業再生計画案に従って、債務の返済を進めていきます。
中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生を支援するために、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき設置された、公正中立な公的機関です。中小企業の事業再生支援の一環として、中小企業再生支援協議会は私的整理のサポートも行っています。
手続きの流れとしては、まず、各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会の窓口に相談します。相談時には、負債や資産の状況、経営状況などが記載された資料を持参し、自社が置かれた状況を分かりやすく説明することが重要です。
中小企業再生支援協議会は、面談や提出資料の分析を通じて問題点を抽出し、問題解決に向けて適切なアドバイスを行います。融資先の金融機関と調整する必要があると判断した場合には、私的整理の手続きに入ります。
その前提として具体的な再生計画を策定する必要がありますが、この段階から中小企業再生支援協議会によるサポートを受けることが可能です。
再生計画の策定ができたら、中小企業再生支援協議会が金融機関等の債権者と債務者との間に入り、再生計画案への合意形成を目指します。全債権者との合意が得られたら、私的整理の成立です。
その後は合意した再生計画に従って債務を返済していきますが、中小企業再生支援協議会が定期的にフォローアップしてくれます。必要に応じて専門的なアドバイスが受けられるので、安心して事業の再建に取り組むことができるでしょう。
RCC企業再生スキーム

RCC企業再生スキームとは、株式会社整理回収機構(RCC)が行う私的整理の手続について、その内容や要件をまとめたもののことです。
RCCは株式会社ではありますが、法律や政府からの要請に基づき業務を行う、公的な使命を帯びた会社です。当初は金融機関の不良債権を整理・回収する株式会社として設立されましたが、その後、金融再生法の改正に伴い、企業再生にかかわる業務も担うようになりました。
手続きの流れとしては、まず、東京または大阪に設置されている相談室に相談します。RCCの専門部局である企業再生部において、企業再生に取り組むのが妥当であると判断された事案については、私的整理の手続きに入ります。
その後、速やかに第1回債権者集会が開催され、そこで債務者は事業や財務の状況、再生の可能性などを説明します。この債権者集会において、債務者およびRCCは個別の債権回収や担保権の実行などを阻止するために、各債権者と一時停止の合意形成を図ります。
一時停止が合意された後、債務者は再生計画案を策定し、RCCへ提出しなければなりません。再生計画案を提出すると第2回債権者集会が開催され、質疑応答や意見交換を経て、対象債権者による決議が行われます。対象債権者全員の同意が得られると、再生計画の成立です。その後は、再生計画に従って債務の返済を進めていきます。
RCC企業再生スキームでは、再生計画成立後も定期的に債権者集会が開催され、債務者はその際に再生計画の実行状況等を報告しなければなりません。
私的整理の4つのメリット

私的整理と法的整理を比べた場合、私的整理のメリットとして以下の4つが挙げられます。
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
世間に知られにくく信用低下が起こりにくい
私的整理には、手続きを行ったことが世間に知られにくく、信用低下が起こりにくいというメリットがあります。
事業を再生するためには、売掛先などの取引先や、買掛先などの一般債権者からの信用を保つことが重要です。世間に対する良好な企業イメージを損なうことも回避したいところでしょう。
私的整理の手続きは裁判所を通さないため、世間に公表されることがありません。そのため、企業イメージの著しい低下を回避できます。
また、手続きの対象とした債権者を除く関係者の債権には影響がないので、迷惑がかかりません。対象とする債権者を適切に選んで手続きを行えば、重要な取引先等からの信用を保ったまま、事業の再生を図ることが可能です。
その点、法的整理ではすべての債権者が手続きの対象となり、重要な取引先が有する債権も強制的に減免の対象となってしまいます。債務の圧縮に成功したとしても、重要な取引先を失ってしまうことも少なくありません。
さらに、特定調停以外の法的整理をすると、官報に企業名や行った手続きの種類などが掲載され、世間に公表されます。これにより、倒産した企業という認識が広まってしまい、企業イメージの低下を招くおそれが強いです。
したがって、事業を円滑に再生するためには、法的整理よりもまず私的整理を検討した方がよいでしょう。
当事者の合意に基づいて柔軟な解決を目指せる
私的整理には、当事者の合意に基づいて柔軟な解決を目指せるというメリットもあります。
私的整理では債務の減免に関する明確なルールはないので、当事者が合意すれば、債務の内容を自由に変更できます。
例えば、私的整理にあまり協力的ではない債権者への返済率は高めにし、協力的な債権者への返済率は低めにするなどして、全体的に遂行可能な再生計画を策定することも考えられるでしょう。
また、私的整理では手続きの対象とする債権者を自由に選べます。合意が見込めない債権者は除外して、合意が見込める債権だけを対象として手続きをすることも可能です。
それに対して、法的整理ではすべての債権者を手続きの対象とし、各債権者を平等に扱わなければなりません。
債務の変更内容も、法律の規定に従って画一的に決めなければならないため、柔軟な解決を目指すことは困難です。
順調に進めば解決までの時間が節約できる
私的整理には長い期間がかかることもありますが、順調に進めば短期間で手続きを終了できるので、解決までの時間を節約できるという点もメリットの1つです。
私的整理では、当事者が合意さえすれば手続きが終了します。企業の状況を示す資料の準備や再生計画案の策定、交渉などにある程度の期間は要しますが、早ければ3ヶ月程度で解決できることもあります。
その点、法的整理では裁判所に申し立てをして、法律で定められた手続きを踏む必要があることから、長い期間がかかることは避けられません。民事再生の手続きは概ね6ヶ月程度で終了しますが、会社更生の手続きは1~3年程度かかるのが一般的です。
速やかに事業を再生したい場合、解決までの時間を節約できる私的整理のメリットは大きいといえるでしょう。
予納金などの負担がなく費用を抑えられる
私的整理は裁判所を通さない手続きであるため、予納金などの負担がなく費用を抑えられるというメリットも挙げられます。
この点、法的整理では裁判所に予納金を納めなければなりません。具体的な予納金の額は企業の規模や債権者数、債務総額などによって異なりますが、一般的に法人の倒産手続きにおける予納金は高額となります。
民事再生では200万円~1200万円程度、会社更生では800万円~3000万円程度が目安です。
ただし、私的整理でも弁護士に手続きを依頼する場合は、弁護士費用がかかることには注意しましょう。
とはいえ、一般的に私的整理では法的整理よりも手続きの負担が軽いため、弁護士費用も低い傾向にあります。そのため、弁護士費用を考慮しても、私的整理の方が費用の負担は圧倒的に軽いことが多いです。
低コストで債務を圧縮し、事業の再生を図れるという点でも、私的整理のメリットは大きいといえるでしょう。
私的整理の2つのデメリット

私的整理には大きなメリットがありますが、以下のように2つのデメリットがあることにも注意が必要です。
それぞれのデメリットについて、詳しくみていきましょう。
債権者の同意が得られない場合がある
私的整理では、債権者の同意が得られない場合があるというデメリットがあります。債務者が策定した再生計画案に同意するかどうかは、債権者の意向次第です。
私的整理の手続きには法的な強制力がないため、債権者に同意を強制することはできません。同意が得られなければ、私的整理に失敗してしまいます。私的整理の交渉に一切応じない債権者もいますし、交渉には応じるものの、同意する前提として厳しい条件を提示してくる債権者もいます。
借り入れてから間もない場合や、長期間にわたって滞納を続けている場合などでは、同意のための条件が厳しくなることが多いです。同意が見込めない債権者は除外して私的整理を行うこともできますが、対象債権者が少なければ債務を圧縮できる幅も小さくなります。
思うように債務を圧縮できなければ、事業再生という目的を果たせなくなることもあるでしょう。主要債権者の同意が得られない場合など、私的整理では目的を果たすことが難しい場合には、法的整理を検討する必要があります。
手続きが不透明だと不信感を持たれる場合がある
私的整理では、手続きの内容が不透明になりがちであり、そのために一部の債権者などから不信感を持たれる場合があるということもデメリットとして挙げられます。
私的整理の手続きの進め方には明確なルールが存在しないため、各債権者と個別に交渉することも可能です。その場合、債権者から見れば再生計画の全体像が不透明となり、他の債権者よりも不利に扱われているのではないかという疑念を抱くことがあります。
このようにして債権者から不信感を持たれると、その債権者の同意を得ることが難しくなりがちです。同意を得られたとしても、取引の継続が難しくなることもあるでしょう。
ひいては、株主など債権者以外の利害関係者(ステークホルダー)からも不信感を持たれて、事業の再生に支障をきたすことになりかねません。
その点、法的整理では裁判所の手続きにおいて全債権者が平等に扱われ、高い透明性が確保されています。したがって、法的整理をすると、債権者から債務の減免という結果に不満を持たれることはあっても、手続きに不信感を持たれることはありません。
私的整理に関するガイドラインに沿って進めよう
私的整理における手続きの不透明さを回避するために、「私的整理に関するガイドライン」に沿って手続きを進めるという方法があります。
私的整理に関するガイドラインとは、公正かつ衡平な私的整理が円滑に成立するように、模範的なルールを定めたものです。
政府が平成13年に発表した緊急経済対策を受けて、経済団体連合会や全国銀行協会などで構成された私的整理に関するガイドライン研究会によって策定・公表されました。
ガイドラインに沿った私的整理では、原則として債権者会議が開催されます。そこで再生計画案の説明や質疑応答などが行われるため、手続きの透明性が確保されるという仕組みです。
参考:私的整理に関するガイドライン研究会|私的整理に関するガイドライン
ただし、私的整理に関するガイドラインは主に大企業を想定した内容となっており、中小企業は利用しにくいという問題点がありました。
そこで、令和4年3月には、政府が設置した中小企業の事業再生等に関する研究会により策定・公表されたのが「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」です。
こちらのガイドラインでも、「第三部 中小企業の事業再生等のための私的整理手続」という章で、透明性を確保した私的整理手続きに関する模範的なルールが示されています。
参考:中小企業の事業再生等に関する研究会|中小企業の事業再生等に関するガイドライン
大企業は私的整理に関するガイドラインを、中小企業は中小企業の事業再生等に関するガイドラインを活用した私的整理を検討するとよいでしょう。
いずれのガイドラインにも法的拘束力はありませんが、金融機関はガイドラインで示されたルールを尊重する傾向にあるので、債権者である金融機関の合意も得られやすくなるはずです。
私的整理に関するよくある質問
最後に、私的整理に関してよくある質問に回答します。
個人でも私的整理を行えますか?
本記事でご紹介した私的整理には明確なルールが存在しないため、個人でも私的整理を行うことも不可能ではありません。個人事業主として比較的規模の大きい事業を営んでいる場合は、私的整理を検討するのもよいでしょう。
ただし、個人が法的手続き以外で債務整理をする場合は、任意整理を行うのが一般的です。
任意整理とは、各債権者と個別に直接交渉を行い、合意によって債務の減免を求める手続きです。一般的には、今後の利息をカットしてもらい、残元金を3~5年の分割で返済していきます。
任意整理においても、合意するかどうかは債権者の意向に委ねられることに注意が必要です。債務者が自分で債権者と交渉すると厳しい条件を提示されることが多いですが、弁護士に任意整理を依頼すると有利な条件で合意が得られやすくなる傾向にあります。