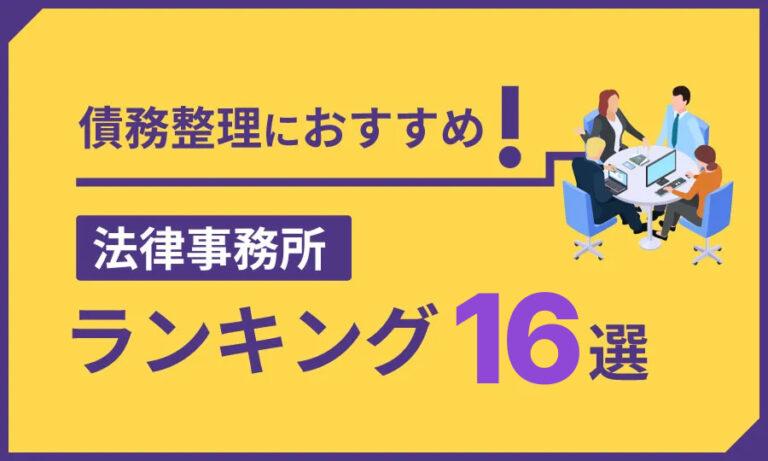破産管財人とは?選任される理由や役割をわかりやすく解説

借金や経営の悪化などにより、返済が現実的ではなくなったために「自己破産」を選択するケースも珍しくありません。
その際、裁判所によって「破産管財人」が選任されるケースがあるのですが、彼らは何をするのか知らないと自己破産に対して不安を抱えるのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産における破産管財人の役割について解説します。
借金や経営の悪化などにより、返済が現実的ではなくなったために「自己破産」を選択するケースも珍しくありません。
その際、裁判所によって「破産管財人」が選任されるケースがあるのですが、彼らは何をするのか知らないと自己破産に対して不安を抱えるのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産における破産管財人の役割について解説します。
破産管財人とは破産者の財産を管理し処分をする権利を持つ人
自己破産に際して選任された破産管財人の主な役割は「裁判所に代わって破産者の財産を管理および処分等を行い、必要な場合には債権者に配当する」ことです。
一般的に「自己破産を行う」ことは、財産がなくなって借金が返済できなくなったから申し立てるという意味合いをイメージする方が多いでしょう。
しかし、本当に1円も現金や資産を持っていないというケースは珍しく、ほとんどの場合はいくらかの現金等の資産を保有した状態で自己破産を申し立てます。
もし、返済に充てられる財産を保有しているにもかかわらず、裁判所が自己破産を認めてしまうと、破産者の債権者が過剰な不利益を被ることになります。
そのため、破産管財人は破産者の現状での財産状態を調査し、それを処分・換価して債権者に対して弁済を行うことで、債権者の権利を守る役割を担うのです。
破産管財人が選任される3つの理由
自己破産において破産管財人が選任されるのは、主に以下の3つの理由が挙げられます。
換価した財産を債権者に公平に分配する
破産管財人の重要な役割の1つは「債権者への公平な弁済」です。
破産者の中には、ある程度の財産を保有したまま自己破産を申し立てているケースがあります。
裁判所は自己破産において最終的に、破産申立人に対して「免責」の可否を判断し、免責が認められればその時点での債務の返済義務がなくなります。
しかし、現金化できる財産が残ったまま免責を認めてしまうと、返済能力が残っているにもかかわらず借金の返済がなくなってしまうことから、債権者が過剰な不利益を被ることになるのです。
そのため、破産管財人は破産者の財産状態を調査して、換価できる財産が残っていないかを確認します。
自己破産においてはすべての財産が没収されるというわけではありませんが、一定以上の金額の財産については現金化され、債権者に対して弁済が行われます。
その際、特定の債権者に対してだけ偏った返済が行われることは、ほかの債権者にとって不平等を生じることになるのです。
たとえば、親戚からの借金や、付き合いの深い取引先などを優先して返済をするケースは珍しくありません。
そうした不平等を防ぐために、破産管財人は破産者の保有する財産を一時的に管理し、処分可能な範囲でこれを売却等して現金化し、原則として債権者に対して債権額に応じて公平に分配を行うことで弁済の不平等を解消します。
悪質な財産隠しを防ぐ
破産管財人は、破産者の財産を徹底的に調査し、「悪質な財産隠し」をしっかりと防ぐ役割を担っています。
破産者の中には、返済するのに相当する財産を保有しているにもかかわらずそれを申告しない悪質なケースもあるのです。
裁判所は、自己破産において「破産者には返済能力がない」ことを認める必要があるため、処分可能な財産が存在している状態で免責を認めるわけにはいきません。
そのため裁判所は、本当に免責を認めるのに相当な経済状態であることを確認したうえで、破産者に対して免責の可否を判断する必要があります。
しかし、裁判所の職員が1人1人の財産状態を確認することは、実務上あまり現実的ではありません。
昨今だと新型コロナウイルスの影響で自己破産をする経営者が多かった経緯もありますので、こうした社会現象や景気などの影響により破産申立人が一時的に増加するケースもあり得ます。
それに対して、裁判所は人員を相当人数増員することは現実的ではありませんから、増えた破産申立人に対して十分な人数の調査員を確保できません。
そこで裁判所は、当事者とは利害関係の存在しない弁護士を破産管財人として選任し、財産状態を確認してもらいます。
悪質な財産隠しであると認められれば、破産法の定める「免責不許可事由」に相当するため、免責ができないだけでなく「詐欺破産罪」という犯罪であると判断される場合もあるのです。
出典:破産法
免責が認められるか詳細に調査する
破産管財人は、裁判所に代わって破産申立人が「免責を与えるのに相当な条件を満たしているかどうか」を判断するための調査を行う役割を担っています。
自己破産のルールについて定めている破産法では、免責不許可事由といって、その条件に当てはまる場合には免責を認めないという決まりがあるのです。
たとえば先ほどの「財産隠し」もその1つですが、それ以外にもさまざまな条件が免責不許可事由として列挙されています。
破産申立人の中には悪質なケースもあり、周到な手段で自身に有利な状況で破産申し立てを行ったり、債権者に不当な不利益を与える目的で工作を行うといったケースもあるのです。
裁判所は自己破産において債権者の利益を最大限保護する必要がありますので、こうしたケースにおいては免責を認めるわけにはいきません。
しかし、前述のとおり裁判所の職員が破産申立人の財産などを調査するにはマンパワーが不足しているため、弁護士を破産管財人として選任し、さまざまな調査や財産の管理を一任するのです。
破産管財人は、現時点での財産状況を確認するだけでなく、直近の資産の動き(預金の引き出しなど)についても詳細に調査を行い、財産隠しなどの悪質な行動がないことを徹底的に確認します。
その結果を裁判所に報告し、免責の可否を判断する判断材料とするのです。
破産管財人が担う5つの業務

裁判所に選任された破産管財人は、主に以下の5つの業務をこなします。
それぞれ順に解説いたします。
破産者の債務額を確定する
破産管財人は、破産者の債務について詳細な調査を行い、債務総額を確定します。
自己破産においては、破産申立人が保有している財産を、可能な範囲で換価して債権者に対して不平等にならないように分配する必要があります。
このとき、破産申し立てに際してすべての債務および債権者を破産者が報告していないケースもあるのです。
後にトラブルになるのを避けるためにもこの時点ですべての債権者を明らかにしておく必要があります。
自己破産時の債権者への弁済は、基本的に「法的に上位の順位にある債権者を優先する」「同じ順位の債権者に対しては債権額に応じて分配する」という性質があるので、債務額を確定しておく必要があるのです。
破産者の財産の管理や換価をする
自己破産においては、破産管財人は破産者の保有するすべての財産を管理し、可能な範囲でこれを換価して債権者への弁済の原資とします。
換価できる財産があるにもかかわらず免責を与えてしまうと、債権回収が不可能になった債権者が過剰な不利益を被ることになります。
そのため、破産管財人は債権者の権利を守るために、破産者が保有する財産をすべて調査して、これを管理して債権者に可能な範囲で弁済を行うための役割を担っているのです。
この「管理する」という行為には、「否認権行使」という行為も含まれます。
自己破産を考えている方の中には、自身の利益を不当に守ろうとしたり、特定の債権者の不利益になるような行為をしようとするケースもあるのです。
たとえば処分可能な財産を減らすことによって債権者への弁済額を減らすという悪意ある目的で、自らの財産が減るような不当な取引をする行為が該当します。
破産管財人は、そうした行為に対して否認権を行使し、その法的効力を失わせる権利を有するのです。
このようにして、破産管財人は自己破産におけるすべての行為が完了するまでの間、破産者の財産について徹底的に管理を行い、免責により債権者が被る不利益を最小限に抑える役割を担っています。
破産の原因を調査し免責許可の見解を示す
破産管財人は、破産者の財産や負債についても調査しますが、そのほかにも破産に至った原因についても詳細に調査を行い、「免責許可の見解を示す」という役割を担っています。
世の中、自己破産を申し立てるにあたっては、さまざまな原因や背景が存在しています。
一般的な原因は「借金」ですが、借金が返せないといっても何を理由にして借金をしたのか、なぜ返済ができなくなったのかといった部分は、人によって大きく異なるのです。
いずれにしても返済の継続が困難であれば自己破産を選択するのは仕方がないという見方もできますが、問題は破産に至った原因によっては、裁判所は免責を与えるべきではないという法律での決まりがあることにあります。
破産法においては、借金の返済義務をなくす免責という行為において、定められている条件をどれか1つでも満たしていると、免責が与えられないという「免責不許可事由」という項目があります。
たとえば、借金の原因が浪費や賭博であった場合、免責不許可事由に該当する可能性があるのです。
ただ、この「免責不許可事由」に当たる場合でも、裁判所の判断で免責を認めることはできるようになっています。これを「裁量免責」と言います。
仮に破産に至った借金の原因が浪費であっても、当時の収入等さまざまな条件も加味して過剰な規模であると判断されなければ、免責不許可事由に相当しないと判断される可能性もありますし、免責不許可事由に該当するとしても裁量免責が認められる場合もあります。
その判断は最終的に裁判所が下しますが、判断材料となる情報を破産管財人が調査し、それをまとめて裁判所に報告することが、破産管財人の仕事の1つなのです。
債権者集会で報告をする
破産管財人には、「債権者集会」という集まりに参加し、必要に応じて説明等を行う義務があります。
債権者集会とは、自己破産した際に破産者に対して債権を有する、いわゆる破産債権者に対して、当該自己破産についての説明を行うのが主な目的です。
この集会には破産管財人のほか、破産者本人と破産申立代理人、担当裁判官と債権者が参加しますが、債権者だけは任意の参加で問題ありません。
債権者集会において、破産管財人は債権者に対して必要事項の説明を行い、債権者からの質問に答えたり破産手続きに関する意見聴取も行います。
なお、破産規模などの条件にもよりますが、破産管財人が選任されるような事例の場合だと、債権者集会は複数回実施されることもよくあります。
その場合、破産管財人は2回目以降の債権者集会において、それまでの破産管財人としての仕事の進捗についても報告します。
また、財産の管理や換価が進んでいれば、債権者に対してその配当についての報告を行うこともあります。
債権者への配当手続きをする
破産管財人は破産者の保有する財産の多くを管理して換価を行い、最終的に現金化した資産を債権者に対して平等になるように分配して処分します(ただし、税金関係など法律上優先して配当される債権者も存在します)。
自己破産においては、破産管財人に認められた一部の財産を除き、換価できる価値のある財産はすべて破産管財人の管理下に置かれます。
破産管財人が管理している財産は破産者が自由に使用したり処分することはできず、これにより特定の債権者にだけ集中的に返済をしたり、債権者の不利益になるように財産の価値を意図的に下げるといった行為ができなくなるのです。
破産管財人は徹底的に調査をすることにより、破産者がその時点で保有する資産総額と負債総額、すべての債権者を確定させることにより、換価することで得られる現金の総額と、それを不平等にならないためにはどのように配当するべきかを計算します。
これを債権者に対して報告し、最終的に確定した処分財産の現金化した総額を債権者に対して配当する手続きを行います。
破産管財人の決め方や費用
破産管財人は、基本的に裁判所が弁護士の中から選任を行います。
破産手続きにおいては、関係者と一切の利害関係のない弁護士から選任する必要があるため、一般的な裁判や個人間のトラブルのように当事者自身が弁護士を選任するようなことはできません。
一般的に、自己破産について規定している破産法に詳しい弁護士が選定される傾向にあります。
破産管財人として活動する弁護士も、当然ながらボランティアでやっているわけではありませんから、破産管財人の仕事に対する報酬が発生します。
その報酬は、破産者が負担するのです。
そのため、自己破産申し立てにおいては、申し立てに際して「予納金」を支払います。
この予納金には破産管財人に対する報酬だけでなく、破産手続きに必要な各種費用も含まれており、一般的な自己破産のケースであれば40万円~50万円が相場です。
なお、負債規模の大きなケースなど破産管財人の負担が大きいケースであれば、100万円以上の予納金が設定されるケースもあります。
ただ、この規模の支払いは破産者にとって結構な金銭的負担になるケースもあるため、一定の条件を満たせば「少額管財事件」として取り扱われ、その場合であれば予納金は20万円程度まで抑えられます。
破産管財人が選任される管財事件になる5つのパターン
自己破産にもさまざまなケースがあり、そのすべてのケースにおいて破産管財人が選任されるわけではありません。
そこで、自己破産において破産管財人が選任される5つのパターン・理由について解説します。
それぞれ順に解説いたします。
一定の財産が残っている場合
破産手続きの申し立てに際して、申立人の保有する財産が一定以上の場合だと、破産管財人が選定されて管財事件として扱われます。
自己破産すると「すべての財産を没収される」というイメージがありますが、実際にはそうではなく、今後生活していくための財産については破産管財人により処分されることなく破産者の保有財産として手元に残しておけます。
一般的に「現金33万円」「20万円以上の財産」が管財人が選定される管財事件のボーダーとなっており、破産申し立てに際してそれ以上の財産を保有していないとわかれば、申し立てと同時に廃止、つまり破産管財人が行う各種手続きを不要として手続きが完了するケースとなるのです。
一方で、その条件を満たさない規模の財産が残っている場合や、財産が残っていないことを明確に証明できない場合については、破産管財人が選任される管財事件として扱われます。
そのため、仮に処分できる規模の財産がない場合でも、弁護士等の専門家に依頼せずに自力で自己破産手続きを申し立てた場合には、管財事件として扱われて破産管財人が選任されるのです。
免責不許可事由に該当している場合
自己破産の申し立てに際して、申告した内容を審査した結果として免責不許可事由に該当していると判断された場合には、破産管財人が選任されるケースが多いです。
前述のとおり、自己破産はすべての申し立て人に対して免責が認められるわけではなく、破産法が定める免責不許可事由に相当する場合だと「返済能力がないことは認める、ただし返済義務は免除しない」という状態になります。
しかし、詳しく調べてみると免責不許可事由に相当しない、あるいは、免責不許可事由に該当するとしても「裁量免責」が相当な場合もありますので、裁判所は安易に免責の不許可を出すわけにもいきません。
そこで、破産管財人を選任し、破産者の詳しい事情を調べるのです。
本来であればこの仕事は裁判所の職員が担うべきなのですが、機動的に調査が可能な人物として破産法に詳しい弁護士を破産管財人として選任し、借金の理由など自己破産に関係するさまざまな事情を調査します。
破産管財人は調査した内容をまとめて裁判所に報告し、裁判所はその報告内容をもとにして免責を与えるかどうかの判断を行います。
代理人に依頼せず個人で自己破産を申請した場合
自己破産においては「同時廃止」と「管財事件」の2つのパターンに分かれるのですが、破産申立人が弁護士などの代理人をたてずに自分自身で自己破産を申し立てた場合は、ほとんどのケースで管財事件として扱われて破産管財人が選任されます。
同時廃止とは、破産申し立ての際に提出された資料等から鑑みて、破産者に処分可能な財産が残っていないことが明確である場合に、申し立てと同時に破産事件の廃止手続きを行うケースです。
免責の決定までに時間がかからないことで、破産者にとっては経済的にも精神的に負担が少ないので好まれるケースが多いのですが、同時廃止が認められるケースとしては、一定の条件を満たす必要があります。
最も重要視される条件は「処分可能な財産が残っていないことが明確である」ことであり、何をもって処分可能な財産が残っていないことを証明できるかという点が重要です。
裁判所は、弁護士が代理人として破産申し立てを行った場合に、弁護士がまとめた資料に重きを置いて信用するため、その資料から処分可能な財産が残っていないことを判別します。
逆に、弁護士を代理人にたてずに破産者自身が破産申し立てを行った場合、申告内容に信ぴょう性が乏しいため、本当に申告内容通りの財産状況であることを調べる必要があるのです。
同時廃止での手続きを希望する場合には、弁護士費用がかかっても代理人をたてて、財産等の状態を調べてもらい、その内容を裁判所に提出してもらって判断を仰ぐ必要があります。
借金の経緯が不明で調査が必要な場合
自己破産を申し立てた際に、破産者の借金の経緯がわからない場合には、破産管財人が選任されることが多いです。
自己破産をする主な理由としては「借金の返済ができなくなった」ことが挙げられます。
借金が積み重なった理由は人によって事情が異なりますが、その事情によっては免責を与えられない可能性があるのです。
主に浪費や賭博を理由とした借金が原因で自己破産をする場合、免責不許可事由に相当するため免責を与えることはできません。
そのため、破産者の借金の経緯が不明な場合、裁判所としては免責不許可事由の有無を問うために調査が必要なのですが、裁判所のマンパワーではすべての破産者に対して借金の理由を調査することは現実的ではないのです。
そこで弁護士を破産管財人として選任し、破産者がどういった経緯で借金が返せなくなったのかを調査して、免責を与えても良いかどうかを判断します。
個人事業主や法人が破産する場合
一般人が自己破産をする場合は、場合によっては同時廃止になって最低限の手続きだけですべての手続きが完了する場合もありますが、「個人事業主」や「法人およびその代表者」が自己破産をする場合は、ほとんどの場合で破産管財人が選任されます。
破産管財人の主な仕事は、破産者の財産と負債の状況を明確にして、処分可能な財産を換価して債権者に平等に分配することです。
一般的な個人の場合、債権者が少なく、処分可能な財産がほとんど残っていない状況であることも多いため、破産管財人を選任することで破産者の負担を増やさずに手続きを完了させるという選択肢もとれます。
しかし、事業を営んでいた個人事業主や法人の場合だと、これらの関係が複雑になるケースが多いのです。
事業が関わる場合の自己破産だと、事業に関わる資産や負債の項目が多く、取引先との関係もありますので調査しなければならない内容が一般人と比較して多くなります。
そのため、債権者への弁済や免責の可否の判断も含めて破産管財人による調査の必要性が極めて高いため、管財事件として扱われて破産管財人が選任されるのです。
破産管財人は厳しい?選任されたときの義務や注意点
自己破産をしても、すべてを失うわけではありません。
しかし、一定以上の財産は債権者への弁済に充てられますし、破産手続き中にはいくつかの制限等の注意するべきポイントもあります。
余計なトラブルを避けるためにも、自己破産手続き中にはどういった点に注意しなければならないのかをしっかりと把握しておきましょう。
それぞれ順に解説いたします。
破産管財人の調査には誠実に協力する
自己破産中には、破産者はさまざまなことをしなければなりません。
やるべきことが多いのは破産管財人のほうですが、破産管財人は単独ではできないことも多く、破産者に対して聞き取りなど調査に協力を求めることも多いです。
もし、破産管財人から何か聞かれたり協力を求められたときには、これに誠実に応えて誠意をもって協力しましょう。
破産者が破産管財人からの要請に応じて誠実に協力することによって、破産手続きやそれに伴う調査がスムーズに進みます。
これにより破産者はより短い期間で破産手続きを完了させて新しい生活を再スタートさせるられ、精神的な負担は最小限に抑えられるでしょう。
逆に、破産管財人からの協力要請に対して非協力的な態度をとると、破産者にとってデメリットが大きいのです。
実は自己破産における免責不許可事由の中には、裁判所や破産管財人から説明を求められた際に、理由もなくこれを拒否した場合は免責不許可事由に該当するという項目があります。
つまり、破産管財人からの協力要請を、正当な理由もなく拒否し続けてしまうと、免責不許可事由に相当して免責を受けられなくなる可能性が高くなるのです。
たとえば、債権者集会には破産者の出席が義務付けられており、病気や入院などの理由がある場合に限り裁判所の許可を得たうえで債権者集会を欠席できます。
しかし、そうした正当な理由もなく裁判所からの許可も得ずに不当に欠席した場合は説明義務違反として免責不許可事由に相当する可能性が高いのです。
トラブルなく破産手続きを完了させるためには、破産管財人からの協力要請には誠実に応え、可能な範囲でしっかりと協力しましょう。
郵便物が一度破産管財人に渡り内容を確認される
自己破産手続き中は、破産者の住所に届く郵便物については、一度破産管財人の手に渡りその内容を確認されるという注意点があります。
「まるで刑務所のようだ」と感じる方もおられるかもしれませんが、自己破産という手続きの性質上、破産者に対して送られた郵便物をすべてチェックすることは破産管財人として重要な仕事の1つなのです。
郵便物の中には、破産者の財産や負債に関係する内容が書かれているものが含まれています。
そのため、破産者の財産や負債の状態を調査してその総額を確定するという役割を担っている破産管財人にとって、破産者の郵便物の内容をチェックすることは重要な意味を持つのです。
また、場合によっては財産隠しなど破産者の悪意の証拠となるような郵便物が見つかる場合もありますので、破産者に対して送られた郵便物は破産管財人の手によって徹底的にチェックされます。
ただし、すべての郵便物が破産管財人のもとに転送されるわけではありません。
たとえば、宅配業者によって配達された荷物は、基本的に破産管財人の管理下に置かれるものではありませんし、同居している家族あての郵便物も基本的にチェックの対象外です。
破産管財人のもとに送られた破産者の郵便物は、内容の確認が終われば、破産者の元へと引き渡されます。
また、急いで手元に置いておきたいという重要な郵便物であれば、破産者が自ら破産管財人のもとへと足を運んで、確認済みの郵便物を回収するという方法もあります。
転居や旅行など移動が制限される
自己破産手続き中には、「転居」および「旅行」といった、遠方への移動が制限されます。
自己破産手続き中は、破産者は裁判所や破産管財人からの説明などの協力要請、債権者集会での債権者への説明など、さまざまなことをしなければなりません。
そんな状況下で、遠方への引っ越しや国内外を問わず旅行をしようものならば、連絡がとれなくなってしまう可能性があります。
場合によっては免責不許可事由の1つである説明義務違反として扱われてしまう可能性もありますので、自己破産手続き中はよほどの理由なく遠方への移動は差し控えて、破産管財人などの人からの連絡には常に応答できるようにしておきましょう。
ただし、自己破産手続き中であっても、絶対に引っ越しや旅行ができないというわけではありません。
正当な理由があり、破産管財人や裁判所からの連絡に支障をきたさないと判断されれば、転居や遠方への移動が許可される可能性があるのです。
たとえば「支払い家賃を抑えるために引っ越す」「仕事の都合で数日間出張する」「親族の冠婚葬祭で遠方に移動する」といった事情であれば、裁判所の許可を得たうえで移動することは十分に可能です。
もし、わからないことがあれば破産管財人や裁判所の担当者に相談するなどして、自身のケースであれば移動しても良いかどうかを確認したうえで、許可を得てから転居・旅行をしましょう。
破産手続き中は制限される職業がある
破産手続き中には、就業が制限される仕事がいくつかあります。
一般的な仕事であれば、自己破産手続き中であっても問題なく仕事を続けることが可能です。
しかし、一部の仕事については、自己破産手続き中は仕事の制限がかかり、免責を受けて復権するまでは仕事ができなくなってしまいます。
これは破産法による規定ではなく、その仕事に関わる法律により制限が設けられているのです。
たとえば「貸金業」の場合、貸金業法第6条の2により、破産手続き中の仕事は制限されています。
出典:貸金業法
免責を認められて復権すれば、再度これらの仕事に就くことは可能です。
なお、破産者に対する仕事の制限は、家族には影響を及ぼしません。
そのため、たとえば夫が自己破産をした場合でも、妻や子どもが仕事の制限を受けることはありませんので安心してください。
また、弁護士や司法書士は自己破産中は制限される職業ではあるのですが、これらの仕事に就くために必要な資格の取得については制限されていませんので、自己破産手続き中に資格をとって、復権後にこれらの仕事に就くという流れは可能です。
破産管財人とは?選任される理由や役割をわかりやすく解説

借金や経営の悪化などにより、返済が現実的ではなくなったために「自己破産」を選択するケースも珍しくありません。
その際、裁判所によって「破産管財人」が選任されるケースがあるのですが、彼らは何をするのか知らないと自己破産に対して不安を抱えるのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産における破産管財人の役割について解説します。
借金や経営の悪化などにより、返済が現実的ではなくなったために「自己破産」を選択するケースも珍しくありません。
その際、裁判所によって「破産管財人」が選任されるケースがあるのですが、彼らは何をするのか知らないと自己破産に対して不安を抱えるのではないでしょうか。
そこで今回は、自己破産における破産管財人の役割について解説します。
破産管財人とは破産者の財産を管理し処分をする権利を持つ人
自己破産に際して選任された破産管財人の主な役割は「裁判所に代わって破産者の財産を管理および処分等を行い、必要な場合には債権者に配当する」ことです。
一般的に「自己破産を行う」ことは、財産がなくなって借金が返済できなくなったから申し立てるという意味合いをイメージする方が多いでしょう。
しかし、本当に1円も現金や資産を持っていないというケースは珍しく、ほとんどの場合はいくらかの現金等の資産を保有した状態で自己破産を申し立てます。
もし、返済に充てられる財産を保有しているにもかかわらず、裁判所が自己破産を認めてしまうと、破産者の債権者が過剰な不利益を被ることになります。
そのため、破産管財人は破産者の現状での財産状態を調査し、それを処分・換価して債権者に対して弁済を行うことで、債権者の権利を守る役割を担うのです。
破産管財人が選任される3つの理由
自己破産において破産管財人が選任されるのは、主に以下の3つの理由が挙げられます。
換価した財産を債権者に公平に分配する
破産管財人の重要な役割の1つは「債権者への公平な弁済」です。
破産者の中には、ある程度の財産を保有したまま自己破産を申し立てているケースがあります。
裁判所は自己破産において最終的に、破産申立人に対して「免責」の可否を判断し、免責が認められればその時点での債務の返済義務がなくなります。
しかし、現金化できる財産が残ったまま免責を認めてしまうと、返済能力が残っているにもかかわらず借金の返済がなくなってしまうことから、債権者が過剰な不利益を被ることになるのです。
そのため、破産管財人は破産者の財産状態を調査して、換価できる財産が残っていないかを確認します。
自己破産においてはすべての財産が没収されるというわけではありませんが、一定以上の金額の財産については現金化され、債権者に対して弁済が行われます。
その際、特定の債権者に対してだけ偏った返済が行われることは、ほかの債権者にとって不平等を生じることになるのです。
たとえば、親戚からの借金や、付き合いの深い取引先などを優先して返済をするケースは珍しくありません。
そうした不平等を防ぐために、破産管財人は破産者の保有する財産を一時的に管理し、処分可能な範囲でこれを売却等して現金化し、原則として債権者に対して債権額に応じて公平に分配を行うことで弁済の不平等を解消します。
悪質な財産隠しを防ぐ
破産管財人は、破産者の財産を徹底的に調査し、「悪質な財産隠し」をしっかりと防ぐ役割を担っています。
破産者の中には、返済するのに相当する財産を保有しているにもかかわらずそれを申告しない悪質なケースもあるのです。
裁判所は、自己破産において「破産者には返済能力がない」ことを認める必要があるため、処分可能な財産が存在している状態で免責を認めるわけにはいきません。
そのため裁判所は、本当に免責を認めるのに相当な経済状態であることを確認したうえで、破産者に対して免責の可否を判断する必要があります。
しかし、裁判所の職員が1人1人の財産状態を確認することは、実務上あまり現実的ではありません。
昨今だと新型コロナウイルスの影響で自己破産をする経営者が多かった経緯もありますので、こうした社会現象や景気などの影響により破産申立人が一時的に増加するケースもあり得ます。
それに対して、裁判所は人員を相当人数増員することは現実的ではありませんから、増えた破産申立人に対して十分な人数の調査員を確保できません。
そこで裁判所は、当事者とは利害関係の存在しない弁護士を破産管財人として選任し、財産状態を確認してもらいます。
悪質な財産隠しであると認められれば、破産法の定める「免責不許可事由」に相当するため、免責ができないだけでなく「詐欺破産罪」という犯罪であると判断される場合もあるのです。
出典:破産法
免責が認められるか詳細に調査する
破産管財人は、裁判所に代わって破産申立人が「免責を与えるのに相当な条件を満たしているかどうか」を判断するための調査を行う役割を担っています。
自己破産のルールについて定めている破産法では、免責不許可事由といって、その条件に当てはまる場合には免責を認めないという決まりがあるのです。
たとえば先ほどの「財産隠し」もその1つですが、それ以外にもさまざまな条件が免責不許可事由として列挙されています。
破産申立人の中には悪質なケースもあり、周到な手段で自身に有利な状況で破産申し立てを行ったり、債権者に不当な不利益を与える目的で工作を行うといったケースもあるのです。
裁判所は自己破産において債権者の利益を最大限保護する必要がありますので、こうしたケースにおいては免責を認めるわけにはいきません。
しかし、前述のとおり裁判所の職員が破産申立人の財産などを調査するにはマンパワーが不足しているため、弁護士を破産管財人として選任し、さまざまな調査や財産の管理を一任するのです。
破産管財人は、現時点での財産状況を確認するだけでなく、直近の資産の動き(預金の引き出しなど)についても詳細に調査を行い、財産隠しなどの悪質な行動がないことを徹底的に確認します。
その結果を裁判所に報告し、免責の可否を判断する判断材料とするのです。
破産管財人が担う5つの業務

裁判所に選任された破産管財人は、主に以下の5つの業務をこなします。
それぞれ順に解説いたします。
破産者の債務額を確定する
破産管財人は、破産者の債務について詳細な調査を行い、債務総額を確定します。
自己破産においては、破産申立人が保有している財産を、可能な範囲で換価して債権者に対して不平等にならないように分配する必要があります。
このとき、破産申し立てに際してすべての債務および債権者を破産者が報告していないケースもあるのです。
後にトラブルになるのを避けるためにもこの時点ですべての債権者を明らかにしておく必要があります。
自己破産時の債権者への弁済は、基本的に「法的に上位の順位にある債権者を優先する」「同じ順位の債権者に対しては債権額に応じて分配する」という性質があるので、債務額を確定しておく必要があるのです。
破産者の財産の管理や換価をする
自己破産においては、破産管財人は破産者の保有するすべての財産を管理し、可能な範囲でこれを換価して債権者への弁済の原資とします。
換価できる財産があるにもかかわらず免責を与えてしまうと、債権回収が不可能になった債権者が過剰な不利益を被ることになります。
そのため、破産管財人は債権者の権利を守るために、破産者が保有する財産をすべて調査して、これを管理して債権者に可能な範囲で弁済を行うための役割を担っているのです。
この「管理する」という行為には、「否認権行使」という行為も含まれます。
自己破産を考えている方の中には、自身の利益を不当に守ろうとしたり、特定の債権者の不利益になるような行為をしようとするケースもあるのです。
たとえば処分可能な財産を減らすことによって債権者への弁済額を減らすという悪意ある目的で、自らの財産が減るような不当な取引をする行為が該当します。
破産管財人は、そうした行為に対して否認権を行使し、その法的効力を失わせる権利を有するのです。
このようにして、破産管財人は自己破産におけるすべての行為が完了するまでの間、破産者の財産について徹底的に管理を行い、免責により債権者が被る不利益を最小限に抑える役割を担っています。
破産の原因を調査し免責許可の見解を示す
破産管財人は、破産者の財産や負債についても調査しますが、そのほかにも破産に至った原因についても詳細に調査を行い、「免責許可の見解を示す」という役割を担っています。
世の中、自己破産を申し立てるにあたっては、さまざまな原因や背景が存在しています。
一般的な原因は「借金」ですが、借金が返せないといっても何を理由にして借金をしたのか、なぜ返済ができなくなったのかといった部分は、人によって大きく異なるのです。
いずれにしても返済の継続が困難であれば自己破産を選択するのは仕方がないという見方もできますが、問題は破産に至った原因によっては、裁判所は免責を与えるべきではないという法律での決まりがあることにあります。
破産法においては、借金の返済義務をなくす免責という行為において、定められている条件をどれか1つでも満たしていると、免責が与えられないという「免責不許可事由」という項目があります。
たとえば、借金の原因が浪費や賭博であった場合、免責不許可事由に該当する可能性があるのです。
ただ、この「免責不許可事由」に当たる場合でも、裁判所の判断で免責を認めることはできるようになっています。これを「裁量免責」と言います。
仮に破産に至った借金の原因が浪費であっても、当時の収入等さまざまな条件も加味して過剰な規模であると判断されなければ、免責不許可事由に相当しないと判断される可能性もありますし、免責不許可事由に該当するとしても裁量免責が認められる場合もあります。
その判断は最終的に裁判所が下しますが、判断材料となる情報を破産管財人が調査し、それをまとめて裁判所に報告することが、破産管財人の仕事の1つなのです。
債権者集会で報告をする
破産管財人には、「債権者集会」という集まりに参加し、必要に応じて説明等を行う義務があります。
債権者集会とは、自己破産した際に破産者に対して債権を有する、いわゆる破産債権者に対して、当該自己破産についての説明を行うのが主な目的です。
この集会には破産管財人のほか、破産者本人と破産申立代理人、担当裁判官と債権者が参加しますが、債権者だけは任意の参加で問題ありません。
債権者集会において、破産管財人は債権者に対して必要事項の説明を行い、債権者からの質問に答えたり破産手続きに関する意見聴取も行います。
なお、破産規模などの条件にもよりますが、破産管財人が選任されるような事例の場合だと、債権者集会は複数回実施されることもよくあります。
その場合、破産管財人は2回目以降の債権者集会において、それまでの破産管財人としての仕事の進捗についても報告します。
また、財産の管理や換価が進んでいれば、債権者に対してその配当についての報告を行うこともあります。
債権者への配当手続きをする
破産管財人は破産者の保有する財産の多くを管理して換価を行い、最終的に現金化した資産を債権者に対して平等になるように分配して処分します(ただし、税金関係など法律上優先して配当される債権者も存在します)。
自己破産においては、破産管財人に認められた一部の財産を除き、換価できる価値のある財産はすべて破産管財人の管理下に置かれます。
破産管財人が管理している財産は破産者が自由に使用したり処分することはできず、これにより特定の債権者にだけ集中的に返済をしたり、債権者の不利益になるように財産の価値を意図的に下げるといった行為ができなくなるのです。
破産管財人は徹底的に調査をすることにより、破産者がその時点で保有する資産総額と負債総額、すべての債権者を確定させることにより、換価することで得られる現金の総額と、それを不平等にならないためにはどのように配当するべきかを計算します。
これを債権者に対して報告し、最終的に確定した処分財産の現金化した総額を債権者に対して配当する手続きを行います。
破産管財人の決め方や費用
破産管財人は、基本的に裁判所が弁護士の中から選任を行います。
破産手続きにおいては、関係者と一切の利害関係のない弁護士から選任する必要があるため、一般的な裁判や個人間のトラブルのように当事者自身が弁護士を選任するようなことはできません。
一般的に、自己破産について規定している破産法に詳しい弁護士が選定される傾向にあります。
破産管財人として活動する弁護士も、当然ながらボランティアでやっているわけではありませんから、破産管財人の仕事に対する報酬が発生します。
その報酬は、破産者が負担するのです。
そのため、自己破産申し立てにおいては、申し立てに際して「予納金」を支払います。
この予納金には破産管財人に対する報酬だけでなく、破産手続きに必要な各種費用も含まれており、一般的な自己破産のケースであれば40万円~50万円が相場です。
なお、負債規模の大きなケースなど破産管財人の負担が大きいケースであれば、100万円以上の予納金が設定されるケースもあります。
ただ、この規模の支払いは破産者にとって結構な金銭的負担になるケースもあるため、一定の条件を満たせば「少額管財事件」として取り扱われ、その場合であれば予納金は20万円程度まで抑えられます。
破産管財人が選任される管財事件になる5つのパターン
自己破産にもさまざまなケースがあり、そのすべてのケースにおいて破産管財人が選任されるわけではありません。
そこで、自己破産において破産管財人が選任される5つのパターン・理由について解説します。
それぞれ順に解説いたします。
一定の財産が残っている場合
破産手続きの申し立てに際して、申立人の保有する財産が一定以上の場合だと、破産管財人が選定されて管財事件として扱われます。
自己破産すると「すべての財産を没収される」というイメージがありますが、実際にはそうではなく、今後生活していくための財産については破産管財人により処分されることなく破産者の保有財産として手元に残しておけます。
一般的に「現金33万円」「20万円以上の財産」が管財人が選定される管財事件のボーダーとなっており、破産申し立てに際してそれ以上の財産を保有していないとわかれば、申し立てと同時に廃止、つまり破産管財人が行う各種手続きを不要として手続きが完了するケースとなるのです。
一方で、その条件を満たさない規模の財産が残っている場合や、財産が残っていないことを明確に証明できない場合については、破産管財人が選任される管財事件として扱われます。
そのため、仮に処分できる規模の財産がない場合でも、弁護士等の専門家に依頼せずに自力で自己破産手続きを申し立てた場合には、管財事件として扱われて破産管財人が選任されるのです。
免責不許可事由に該当している場合
自己破産の申し立てに際して、申告した内容を審査した結果として免責不許可事由に該当していると判断された場合には、破産管財人が選任されるケースが多いです。
前述のとおり、自己破産はすべての申し立て人に対して免責が認められるわけではなく、破産法が定める免責不許可事由に相当する場合だと「返済能力がないことは認める、ただし返済義務は免除しない」という状態になります。
しかし、詳しく調べてみると免責不許可事由に相当しない、あるいは、免責不許可事由に該当するとしても「裁量免責」が相当な場合もありますので、裁判所は安易に免責の不許可を出すわけにもいきません。
そこで、破産管財人を選任し、破産者の詳しい事情を調べるのです。
本来であればこの仕事は裁判所の職員が担うべきなのですが、機動的に調査が可能な人物として破産法に詳しい弁護士を破産管財人として選任し、借金の理由など自己破産に関係するさまざまな事情を調査します。
破産管財人は調査した内容をまとめて裁判所に報告し、裁判所はその報告内容をもとにして免責を与えるかどうかの判断を行います。
代理人に依頼せず個人で自己破産を申請した場合
自己破産においては「同時廃止」と「管財事件」の2つのパターンに分かれるのですが、破産申立人が弁護士などの代理人をたてずに自分自身で自己破産を申し立てた場合は、ほとんどのケースで管財事件として扱われて破産管財人が選任されます。
同時廃止とは、破産申し立ての際に提出された資料等から鑑みて、破産者に処分可能な財産が残っていないことが明確である場合に、申し立てと同時に破産事件の廃止手続きを行うケースです。
免責の決定までに時間がかからないことで、破産者にとっては経済的にも精神的に負担が少ないので好まれるケースが多いのですが、同時廃止が認められるケースとしては、一定の条件を満たす必要があります。
最も重要視される条件は「処分可能な財産が残っていないことが明確である」ことであり、何をもって処分可能な財産が残っていないことを証明できるかという点が重要です。
裁判所は、弁護士が代理人として破産申し立てを行った場合に、弁護士がまとめた資料に重きを置いて信用するため、その資料から処分可能な財産が残っていないことを判別します。
逆に、弁護士を代理人にたてずに破産者自身が破産申し立てを行った場合、申告内容に信ぴょう性が乏しいため、本当に申告内容通りの財産状況であることを調べる必要があるのです。
同時廃止での手続きを希望する場合には、弁護士費用がかかっても代理人をたてて、財産等の状態を調べてもらい、その内容を裁判所に提出してもらって判断を仰ぐ必要があります。
借金の経緯が不明で調査が必要な場合
自己破産を申し立てた際に、破産者の借金の経緯がわからない場合には、破産管財人が選任されることが多いです。
自己破産をする主な理由としては「借金の返済ができなくなった」ことが挙げられます。
借金が積み重なった理由は人によって事情が異なりますが、その事情によっては免責を与えられない可能性があるのです。
主に浪費や賭博を理由とした借金が原因で自己破産をする場合、免責不許可事由に相当するため免責を与えることはできません。
そのため、破産者の借金の経緯が不明な場合、裁判所としては免責不許可事由の有無を問うために調査が必要なのですが、裁判所のマンパワーではすべての破産者に対して借金の理由を調査することは現実的ではないのです。
そこで弁護士を破産管財人として選任し、破産者がどういった経緯で借金が返せなくなったのかを調査して、免責を与えても良いかどうかを判断します。
個人事業主や法人が破産する場合
一般人が自己破産をする場合は、場合によっては同時廃止になって最低限の手続きだけですべての手続きが完了する場合もありますが、「個人事業主」や「法人およびその代表者」が自己破産をする場合は、ほとんどの場合で破産管財人が選任されます。
破産管財人の主な仕事は、破産者の財産と負債の状況を明確にして、処分可能な財産を換価して債権者に平等に分配することです。
一般的な個人の場合、債権者が少なく、処分可能な財産がほとんど残っていない状況であることも多いため、破産管財人を選任することで破産者の負担を増やさずに手続きを完了させるという選択肢もとれます。
しかし、事業を営んでいた個人事業主や法人の場合だと、これらの関係が複雑になるケースが多いのです。
事業が関わる場合の自己破産だと、事業に関わる資産や負債の項目が多く、取引先との関係もありますので調査しなければならない内容が一般人と比較して多くなります。
そのため、債権者への弁済や免責の可否の判断も含めて破産管財人による調査の必要性が極めて高いため、管財事件として扱われて破産管財人が選任されるのです。
破産管財人は厳しい?選任されたときの義務や注意点
自己破産をしても、すべてを失うわけではありません。
しかし、一定以上の財産は債権者への弁済に充てられますし、破産手続き中にはいくつかの制限等の注意するべきポイントもあります。
余計なトラブルを避けるためにも、自己破産手続き中にはどういった点に注意しなければならないのかをしっかりと把握しておきましょう。
それぞれ順に解説いたします。
破産管財人の調査には誠実に協力する
自己破産中には、破産者はさまざまなことをしなければなりません。
やるべきことが多いのは破産管財人のほうですが、破産管財人は単独ではできないことも多く、破産者に対して聞き取りなど調査に協力を求めることも多いです。
もし、破産管財人から何か聞かれたり協力を求められたときには、これに誠実に応えて誠意をもって協力しましょう。
破産者が破産管財人からの要請に応じて誠実に協力することによって、破産手続きやそれに伴う調査がスムーズに進みます。
これにより破産者はより短い期間で破産手続きを完了させて新しい生活を再スタートさせるられ、精神的な負担は最小限に抑えられるでしょう。
逆に、破産管財人からの協力要請に対して非協力的な態度をとると、破産者にとってデメリットが大きいのです。
実は自己破産における免責不許可事由の中には、裁判所や破産管財人から説明を求められた際に、理由もなくこれを拒否した場合は免責不許可事由に該当するという項目があります。
つまり、破産管財人からの協力要請を、正当な理由もなく拒否し続けてしまうと、免責不許可事由に相当して免責を受けられなくなる可能性が高くなるのです。
たとえば、債権者集会には破産者の出席が義務付けられており、病気や入院などの理由がある場合に限り裁判所の許可を得たうえで債権者集会を欠席できます。
しかし、そうした正当な理由もなく裁判所からの許可も得ずに不当に欠席した場合は説明義務違反として免責不許可事由に相当する可能性が高いのです。
トラブルなく破産手続きを完了させるためには、破産管財人からの協力要請には誠実に応え、可能な範囲でしっかりと協力しましょう。
郵便物が一度破産管財人に渡り内容を確認される
自己破産手続き中は、破産者の住所に届く郵便物については、一度破産管財人の手に渡りその内容を確認されるという注意点があります。
「まるで刑務所のようだ」と感じる方もおられるかもしれませんが、自己破産という手続きの性質上、破産者に対して送られた郵便物をすべてチェックすることは破産管財人として重要な仕事の1つなのです。
郵便物の中には、破産者の財産や負債に関係する内容が書かれているものが含まれています。
そのため、破産者の財産や負債の状態を調査してその総額を確定するという役割を担っている破産管財人にとって、破産者の郵便物の内容をチェックすることは重要な意味を持つのです。
また、場合によっては財産隠しなど破産者の悪意の証拠となるような郵便物が見つかる場合もありますので、破産者に対して送られた郵便物は破産管財人の手によって徹底的にチェックされます。
ただし、すべての郵便物が破産管財人のもとに転送されるわけではありません。
たとえば、宅配業者によって配達された荷物は、基本的に破産管財人の管理下に置かれるものではありませんし、同居している家族あての郵便物も基本的にチェックの対象外です。
破産管財人のもとに送られた破産者の郵便物は、内容の確認が終われば、破産者の元へと引き渡されます。
また、急いで手元に置いておきたいという重要な郵便物であれば、破産者が自ら破産管財人のもとへと足を運んで、確認済みの郵便物を回収するという方法もあります。
転居や旅行など移動が制限される
自己破産手続き中には、「転居」および「旅行」といった、遠方への移動が制限されます。
自己破産手続き中は、破産者は裁判所や破産管財人からの説明などの協力要請、債権者集会での債権者への説明など、さまざまなことをしなければなりません。
そんな状況下で、遠方への引っ越しや国内外を問わず旅行をしようものならば、連絡がとれなくなってしまう可能性があります。
場合によっては免責不許可事由の1つである説明義務違反として扱われてしまう可能性もありますので、自己破産手続き中はよほどの理由なく遠方への移動は差し控えて、破産管財人などの人からの連絡には常に応答できるようにしておきましょう。
ただし、自己破産手続き中であっても、絶対に引っ越しや旅行ができないというわけではありません。
正当な理由があり、破産管財人や裁判所からの連絡に支障をきたさないと判断されれば、転居や遠方への移動が許可される可能性があるのです。
たとえば「支払い家賃を抑えるために引っ越す」「仕事の都合で数日間出張する」「親族の冠婚葬祭で遠方に移動する」といった事情であれば、裁判所の許可を得たうえで移動することは十分に可能です。
もし、わからないことがあれば破産管財人や裁判所の担当者に相談するなどして、自身のケースであれば移動しても良いかどうかを確認したうえで、許可を得てから転居・旅行をしましょう。
破産手続き中は制限される職業がある
破産手続き中には、就業が制限される仕事がいくつかあります。
一般的な仕事であれば、自己破産手続き中であっても問題なく仕事を続けることが可能です。
しかし、一部の仕事については、自己破産手続き中は仕事の制限がかかり、免責を受けて復権するまでは仕事ができなくなってしまいます。
これは破産法による規定ではなく、その仕事に関わる法律により制限が設けられているのです。
たとえば「貸金業」の場合、貸金業法第6条の2により、破産手続き中の仕事は制限されています。
出典:貸金業法
免責を認められて復権すれば、再度これらの仕事に就くことは可能です。
なお、破産者に対する仕事の制限は、家族には影響を及ぼしません。
そのため、たとえば夫が自己破産をした場合でも、妻や子どもが仕事の制限を受けることはありませんので安心してください。
また、弁護士や司法書士は自己破産中は制限される職業ではあるのですが、これらの仕事に就くために必要な資格の取得については制限されていませんので、自己破産手続き中に資格をとって、復権後にこれらの仕事に就くという流れは可能です。