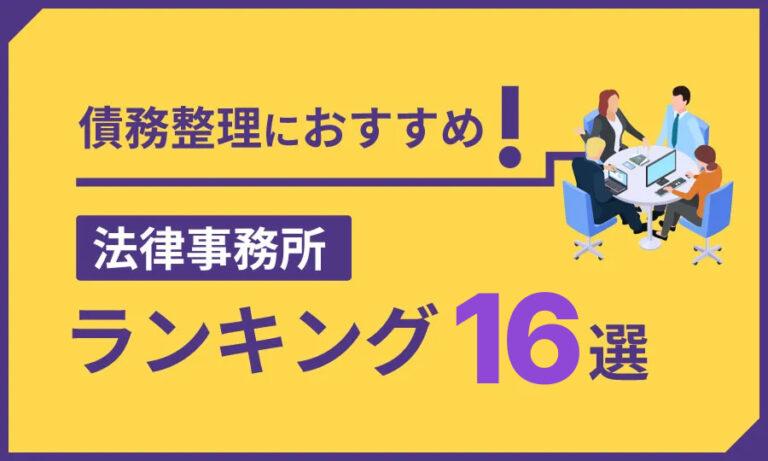自己破産できる3つの条件とは?できない確率や対処法を解説

自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続きのことです。
養育費や税金などの非免責債権を除く全ての借金をゼロにできるので、借金だらけで生活が成り立たなくなってしまった人を救済する手法にもなっています。
ただし、借金がある人全員が自己破産できるとは限らないので注意しましょう。
本記事では、自己破産できる3つ条件について解説します。
自己破産が認められる条件は3つ

大前提として、自己破産を認めてもらうためには以下3つの条件を全て満たしている必要があります。
以下でそれぞれ詳しく解説します。
支払不能であること
自己破産は、支払不能である状態で初めて認められます。
「借金を返済できる見込みがない」「完全な支払不能状態に陥っている」と客観的にわかる状態でないと、基本的に申請できません。
- 債務の総額・内容
- 資産の総額・内容
- 収入
- 家族構成
- 生活状況
- 債務負担するに至る事情
資産・収入を大幅に上回る債務あり、誰がどう見ても返済できない状態であれば、自己破産の申請が通りやすくなります。
反対に、収入に対して債務の割合が低く、「一人暮らし」「同居家族の資産は十分にある」「生活レベルが高い」という状態であれば自己破産は認められないでしょう。
自己破産の可否は上記の要素を総合的に加味して決められるため基準となる数値はありませんが、一般的には債務の総額が年収の3分の1を超えている場合に認められることが多いです。
借金の総額は100〜300万円が多い
自己破産の申請が通る人は、借金の総額が概ね100万円から300万円程度であることが多いです。
| 自己破産者の負債額帯 | 割合 |
|---|---|
| 100万円未満 | 8.39% |
| 100〜200万円未満 | 13.87% |
| 200〜300万円未満 | 14.52% |
| 300〜400万円未満 | 11.13% |
| 400〜500万円未満 | 7.42% |
| 500〜600万円未満 | 5.56% |
| 600〜700万円未満 | 4.76% |
| 700〜1,000万円未満 | 8.71% |
| 1,000〜2,000万円未満 | 11.05% |
| 2,000〜3,000万円未満 | 5.65% |
| 3,000〜4,000万円未満 | 2.50% |
| 4,000〜5,000万円未満 | 1.05% |
| 5,000万〜1億円未満 | 1.77% |
| 1億円以上 | 2.90% |
| 不明 | 0.73% |
実際には収入や資産状況も加味して決定されるため、負債額だけで一律に判断することはできません。
とはいえ借金が100~300万円あり、どうしても返済できず苦しんでいるのであれば自己破産を検討してよいでしょう。
借金が非免責債権だけではないこと
自己破産するには、今ある借金が「非免責債権」だけでないことが重要です。
非免責債権とは
非免責債権とは、自己破産の手続きをしても支払義務が免除されない債権のこと。
代表的な非免責債権として、以下が当てはまります。
- 税金
- 社会保険料
- 公共料金
- 損害賠償金
- 慰謝料
- 養育費
- 罰金
- 従業員への給与
上記の債務は自己破産した後も免除されないため、引き続き支払い続ける必要があります。
借金が非免責債権だけの場合、実質的に自己破産しても意味がないため申請も通らないのが現状です。
免責不許可事由に該当しないこと
自己破産する際は、債務・資産・収入の状況だけでなく「債務負担するに至る事情」も考慮されます。
免責不許可事由に該当していると債務負担するに至る事情がないと判断されてしまい、自己破産の申請が通りません。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因・事由のこと。
代表的な免責不許可事由として、以下が当てはまります。
- ギャンブルが原因で莫大な借金を負った場合
- 支払不能状態にありながら金銭売買などの取引をした場合
- 自己の資産・収入を不当に過少申告し隠蔽した場合
- 裁判所に対して虚偽の申告・説明をした場合
- 自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
- 支払能力がないにも関わらず資金状況を偽って借金している場合
- 裁判所・管財人に非協力的な場合
- クレジットカードの現金化など不当な債務負担をした場合
つまり、自己責任の割合が高い申請は原則として認められないので注意しましょう。
「本格的に首が回らなくなったら自己破産すればいいや」という考え方を防ぐものであり、借金するやむを得ない事情がないときは自己破産もできません。
自己破産できない5つのケース
ここでは、自己破産できないケースについてより詳しく解説していきます。
「自己破産できないなんて知らなかった」という思わぬ落とし穴を防ぐためにも、具体的な事例をチェックしていきましょう。
借金の額が少額で支払不能ではない
借金の額が少額で、そもそも支払不能ではないときは自己破産できません。
自己破産は「どう努力しても支払いができない状態にある人」を対象とした救済措置のひとつであり、誰もが自由に利用できるわけでない点に注意しましょう。
債務があって苦しんでいても、まずは資産や労働力を使ってコツコツ返済していく自己努力が求められます。
税金の滞納や保険料の滞納しかない
滞納した税金・社会保険料などは「非免責債権」に該当するため、債務がこれしかない場合は自己破産できません。
同様に、損害賠償金・慰謝料・養育費なども「非免責債権」に該当するので注意しましょう。
自己破産しても非免責債権である金額は免除されないため、自己破産する意味がありません。
非免責債権も非免責債権以外も含む申請であれば申請が通るかもしれませんが、完全に借金をゼロにすることはできない点に注意しましょう。
浪費やギャンブルの借金が大部分を占める
過度な浪費・ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当するため、自己破産できません。
自己破産とは本来「やむを得ない事情により借金が膨らんでしまった人」を救済するための措置として施行されています。
自己責任の割合が高い浪費・ギャンブルが原因の場合、「同情の余地がない」と思われてしまうのです。
ただし、ギャンブル依存症やショッピング依存症の治療中であり、医師からの診断・指示が別に出ている場合は考慮してもらえる可能性があります。
過去7年間に自己破産したことがある
過去7年間に自己破産したことがある場合、もう一度自己破産することはできません。
一度救済してもらっても繰り返し借金を作ってしまう人の場合、もはや自己責任であるとみなされてしまいます。
また、7年が経過していても2回目の自己破産申請時には前回より厳しい基準が設けられるので注意しましょう。
どうしても借金せざるを得ない理由がない限り、2度目の申請はかなりハードルが高くなります。
裁判所への予納金が払えない
裁判所への予納金が払えない場合、自己破産の手続き自体を進めることができません。
予納金とは自己破産にかかる費用のことで、手続きをする際に最低限必要なお金です。書類発行にかかる費用、裁判官の人件費、官報公告費用、手数料などが含まれます。
自己破産における予納金は、申請者の状況に応じて決定されます。
資産も収入もなくかなり切羽詰まっている場合、予納金は1万円前後になることが多いです。
反対に、処分できる財産がまだある場合は20万円程かかることもあり、人による差が大きいのが特徴です。
自己破産ができない確率は?
自己破産ができない確率は2%以下と言われています。
非免責債権や免責不許可事由など除外項目があるとはいえ、自己破産申請のほとんどが認められていることがわかります。
これには、「もう借金の返済はできないという状況のなかで新たに人生をスタートさせる方法」という自己破産の性質が関係しています。
切羽詰まった人を見捨ててしまうとより状況が悪化してしまうことを考えると、自己破産を認めるしかないことも多いのです。
2020年の調査結果では不許可はゼロ
2020年の調査結果を見ると、自己破産申請をして「不許可」だったケースはゼロだとわかりました。
| 免責申立の結果 | 20年調査 | 17年調査 | 14年調査 | 11年調査 | 8年調査 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 | 96.85% | 96.77% | 96.44% | 96.67% | 97.85% | 96.91% |
| 不許可 | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 0.16% |
| 却下・棄却 | 0.16% | 0.08% | 0.24% | 0.08% | 0.08% | 0.16% |
| 取り下げ | 1.37% | 2.34% | 2.75% | 2.11% | 1.57% | 2.02% |
| 死亡終了 | 0.32% | 0.08% | 0.32% | 0.24% | 0.08% | 0.20% |
| 不明 | 1.29% | 0.16% | 0.24% | 0.65% | 0.25% | 0.51% |
つまり、自己破産を申請して認められなかった人はゼロ人だった、ということです。
「自己破産ができない確率2%」に含まれているのは、ほとんどが本人による取り下げや死亡終了が中心とわかりました。
自己破産申請が通らないことは、あまり心配しすぎなくてよいでしょう。
ギャンブルや浪費が原因の場合でも、よほどのケースを除き許可されているのが現状です。
自己破産しない方がいい3つのケース
自己破産は債務を見直して計画的な資金計画にする大切な制度ですが、自己破産しない方が良いケースも存在します。
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 資格制限のある職業に就いている
- 持ち家などどうしても残したい財産がある
上記に該当する場合、自己破産には慎重になった方がよいでしょう。
保証人に迷惑をかけたくない
自己破産をしても、連帯保証人や保証人(通常保証人)の支払義務はなくなりません。
債務者である自分が自己破産してしまった場合、当然ながら返済義務は連帯保証人・保証人(通常保証人)へと移ります。
自分の借金を完全に肩代わりさせてしまうことになるため、保証人に迷惑をかけたくないときの自己破産は慎重になった方がよいでしょう。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、「催告抗弁権」を持たない保証人のこと。主債務者と同じ立場でお金を借りている状態になるため、主債務者の資産状況と関係なく返済する義務を負います。
つまり、連帯保証人は自己破産の有無と関係なく返済義務を有しているのが特徴です。
極論、主債務者が支払い負担を避けるため夜逃げしてしまったり、借金の返済をなあなあにして踏み倒したりするだけでも、連帯保証人に請求される可能性があります。
自己破産したとなればほぼ確実に連絡されるだけでなく、全額の一括返済が求められるケースもあるので注意しましょう。
保証人(通常保証人)とは
保証人(通常保証人)とは、「催告抗弁権」を持つ保証人のこと。催告抗弁権とは、保証人(通常保証人)が債権者から債務の履行を請求された際、先に債務者に対して返済を請求するように請求できる権利のことです。
つまり、連帯保証人であれば、保証人になっている分の返済を求められても「先に本人へ請求してくれ」と依頼できます。
とはいえ連帯保証人も保証人(通常保証人)も、もともとお金を借りている主債務者が返済不能に陥ったときは、自分で返済する義務を持ちます。
自己破産が認められるケースはよほど資産状況が悪化していると考えられるので、どちらの保証人でも借金の肩代わりが必要となってくるでしょう。
| 比較項目 | 連帯保証人 | 保証人 |
|---|---|---|
| 責任 | ほぼ主債務者と同じ | 保証債務(主債務者と別) |
| 返済時期 | 請求された時 | 主債務者が返済困難であるとき |
| 危険範囲 | 借りたお金の全額 | 保証人の人数で割った金額 |
| 差押え | 反論できない | 主債務者の後 |
他にも、連帯保証人と保証人(通常保証人)との間には、返済するべき時期や危険範囲の差があります。
より責任が重く、問答無用で請求されてしまうのが連帯保証人と考えておくとよいでしょう。
ただし、連帯保証人・保証人(通常保証人)つきの借金だけを優先的に返済することは「偏頗弁済」に当たり、自己破産手続きができなくなる恐れがあります。
偏頗弁済とは
「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とは、借金の返済ができなくなっているにもかかわらず、一部の債権者にだけ優先的に返済や担保提供などをしてしまうことです。
自己破産や個人再生をするときは全ての債務者を平等に扱う必要があるため、特定の債務だけを優先して返済するおとはできません。
「保証人に迷惑をかけたくないから先に返済しておこう」という打算はほぼ認められないと考えましょう。
資格制限のある職業に就いている
資格制限のある職業に就いている場合、自己破産することで一定期間資格や職業の制限を受けることがあります。
資格制限とは
「資格制限」とは、一時的に資格の取得・登録や資格を使った仕事ができなくなること。破産法ではなく各資格・職業に関する法律に規定されており、自己破産者となることで仕事に制限が加えられます。
資格制限のある代表的な職種は、以下の通りです。
| 分類 | 資格・職業 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 士業 | 弁護士 | 弁護士法7条4号 |
| 弁理士 | 弁理士法8条10号 | |
| 公認会計士 | 公認会計士法4条4号 | |
| 税理士 | 税理士法4条2号 | |
| 司法書士 | 司法書士法5条3号 | |
| 行政書士 | 行政書士法2条の2第3号 | |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法5条2号 | |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法5条3号 | |
| 通関士 | 通関業法第31条第2項1号 |
いわゆる「士業」と呼ばれる専門職では、ほとんど資格制限が適用されてしまいます。
自己破産の申立から4~6ヶ月程度で資格制限が解除されるのがほとんどですが、詳細は自身の資格に関連する根拠法令を参照しながら確認しましょう。
なお、資格制限が適用された場合、当然ながらその期間中は資格が必要な仕事や「独占業務」ができません。
独占業務とは
「独占業務」とは、その資格を持っていないとできない業務のこと。わかりやすい例でいうと、弁護士における裁判書類作成、医師・看護師等による医療行為が該当します。
資格制限を受けたからといって即座に解雇されることはないものの、実務が大幅に制限されてしまうため、自己破産の事実が職場に知れ渡ってしまうことも多いです。
また、直接的な人事評価はされずとも、「私生活に不安がある」「期間中の実務に大きな穴を作った」という印象が査定に影響するケースも少なくありません。
自己破産期間中は本当にサポート業務を担当するだけで問題ないか、自分の仕事を振り返りながらシミュレーションしてみましょう。
自己破産できないときはどうする?
最後に、自己破産できないときの対策を紹介します。
- 安定した収入があれば個人再生を検討する
- 裁判所を通さず任意整理で交渉する
「自己破産ができなかったから人生終わった…」と考える必要はありません。
他にも債務の見直しをする手法があるので、下記を確認してみましょう。
安定した収入があれば個人再生を検討する
安定した収入があれば、個人再生がおすすめです。
個人再生とは
「個人再生」とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手法のこと。
個人再生は返済が必要な金額を概ね5分の1程度にまで圧縮できるのが特徴であり、残った金額についてはその後も継続して返済を続けていきます。
自己破産と違って資格制限や財産処分を受ける必要がなく、実生活への影響を最小限に抑えられるのが強みです。
| 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 借金減額 | 概ね5分の1まで圧縮 | 全額免除 |
| 家について | 住宅ローン特則が利用できる場合は、手放さなくてOK | 処分される |
| 車について | ローンが残っていたら、手放す可能性あり | ローンが残っていない場合でも、時価が20万円超の場合は処分対象となる |
| 資格制限 | なし | あり |
| 免責不許可事由 | なし | あり |
自己破産のようにギャンブルによる借金などの免責不許可事由などがないのもメリットのひとつ。
なお、個人再生後に残る返済額については、以下3つの要素から決定されます。
| ①負債額から算出する金額(最低弁済基準) | 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額 負債額が100万円以上500万円以下の場合は、100万円 負債額が500万円超1500万円以下の場合は、負債額の5分の1 負債額が1500万円超3000万円以下の場合は、300万円 負債額が3000万円超5000万円以下の場合は、負債額の10分の1 |
|---|---|
| ②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準) | 不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額。 |
| ③収入から算出する金額 | 収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額。 |
資産も収入もなく完全に返すアテがないのであれば自己破産するしかありませんが、収入があるときは個人再生の方がダメージを減らせるのでおすすめです。
裁判所を通さず任意整理で交渉する
裁判所を通さず、任意整理として交渉しながら返済額を減らしていく方法もあります。
任意整理とは
「任意整理」とは「債務整理」とも呼ばれる手法であり、弁護士が貸付業者と交渉することで返済額を減額してもらう手続きのこと。
原則として利息の交渉をして返済額を抑える手法であり、元本そのものは減らない点に注意が必要です。
個人再生と違って一部の債権者だけと交渉することもできるので自由度が高く、裁判所を介さないため手続きも比較的容易です。
| 任意整理 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 裁判所 | 裁判所を介さない | 裁判所を介する |
| 債務の減額 | 利息が減額されるのみで元本は減らない | 全額免除 |
| 毎月の返済 | 月々の支払が軽くなる | 返済不要になる |
| 財産処分 | なし | あり |
| 保証人への影響 | なし | あり |
とはいえ自分ひとりで任意整理をするハードルが高い!と感じる人も多いので、困ったときは弁護士に相談しましょう。
その他、簡易裁判所における訴訟代理権を付与された「認定司法書士」と呼ばれる司法書士であれば、債権額140万円以下の任意整理に限り担当できます。
まとめ
「本当に首が回らなくなったら自己破産すればいい」と考える人もいますが、実は自己破産したくてもできないケースがあるので注意が必要です。
特に、借金の内容や理由によっては申請が却下されてしまうこともあるので、事前に条件を確認しておくことが大切です。
自己破産できる3つの条件とは?できない確率や対処法を解説

自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続きのことです。
養育費や税金などの非免責債権を除く全ての借金をゼロにできるので、借金だらけで生活が成り立たなくなってしまった人を救済する手法にもなっています。
ただし、借金がある人全員が自己破産できるとは限らないので注意しましょう。
本記事では、自己破産できる3つ条件について解説します。
自己破産が認められる条件は3つ

大前提として、自己破産を認めてもらうためには以下3つの条件を全て満たしている必要があります。
以下でそれぞれ詳しく解説します。
支払不能であること
自己破産は、支払不能である状態で初めて認められます。
「借金を返済できる見込みがない」「完全な支払不能状態に陥っている」と客観的にわかる状態でないと、基本的に申請できません。
- 債務の総額・内容
- 資産の総額・内容
- 収入
- 家族構成
- 生活状況
- 債務負担するに至る事情
資産・収入を大幅に上回る債務あり、誰がどう見ても返済できない状態であれば、自己破産の申請が通りやすくなります。
反対に、収入に対して債務の割合が低く、「一人暮らし」「同居家族の資産は十分にある」「生活レベルが高い」という状態であれば自己破産は認められないでしょう。
自己破産の可否は上記の要素を総合的に加味して決められるため基準となる数値はありませんが、一般的には債務の総額が年収の3分の1を超えている場合に認められることが多いです。
借金の総額は100〜300万円が多い
自己破産の申請が通る人は、借金の総額が概ね100万円から300万円程度であることが多いです。
| 自己破産者の負債額帯 | 割合 |
|---|---|
| 100万円未満 | 8.39% |
| 100〜200万円未満 | 13.87% |
| 200〜300万円未満 | 14.52% |
| 300〜400万円未満 | 11.13% |
| 400〜500万円未満 | 7.42% |
| 500〜600万円未満 | 5.56% |
| 600〜700万円未満 | 4.76% |
| 700〜1,000万円未満 | 8.71% |
| 1,000〜2,000万円未満 | 11.05% |
| 2,000〜3,000万円未満 | 5.65% |
| 3,000〜4,000万円未満 | 2.50% |
| 4,000〜5,000万円未満 | 1.05% |
| 5,000万〜1億円未満 | 1.77% |
| 1億円以上 | 2.90% |
| 不明 | 0.73% |
実際には収入や資産状況も加味して決定されるため、負債額だけで一律に判断することはできません。
とはいえ借金が100~300万円あり、どうしても返済できず苦しんでいるのであれば自己破産を検討してよいでしょう。
借金が非免責債権だけではないこと
自己破産するには、今ある借金が「非免責債権」だけでないことが重要です。
非免責債権とは
非免責債権とは、自己破産の手続きをしても支払義務が免除されない債権のこと。
代表的な非免責債権として、以下が当てはまります。
- 税金
- 社会保険料
- 公共料金
- 損害賠償金
- 慰謝料
- 養育費
- 罰金
- 従業員への給与
上記の債務は自己破産した後も免除されないため、引き続き支払い続ける必要があります。
借金が非免責債権だけの場合、実質的に自己破産しても意味がないため申請も通らないのが現状です。
免責不許可事由に該当しないこと
自己破産する際は、債務・資産・収入の状況だけでなく「債務負担するに至る事情」も考慮されます。
免責不許可事由に該当していると債務負担するに至る事情がないと判断されてしまい、自己破産の申請が通りません。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因・事由のこと。
代表的な免責不許可事由として、以下が当てはまります。
- ギャンブルが原因で莫大な借金を負った場合
- 支払不能状態にありながら金銭売買などの取引をした場合
- 自己の資産・収入を不当に過少申告し隠蔽した場合
- 裁判所に対して虚偽の申告・説明をした場合
- 自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
- 支払能力がないにも関わらず資金状況を偽って借金している場合
- 裁判所・管財人に非協力的な場合
- クレジットカードの現金化など不当な債務負担をした場合
つまり、自己責任の割合が高い申請は原則として認められないので注意しましょう。
「本格的に首が回らなくなったら自己破産すればいいや」という考え方を防ぐものであり、借金するやむを得ない事情がないときは自己破産もできません。
自己破産できない5つのケース
ここでは、自己破産できないケースについてより詳しく解説していきます。
「自己破産できないなんて知らなかった」という思わぬ落とし穴を防ぐためにも、具体的な事例をチェックしていきましょう。
借金の額が少額で支払不能ではない
借金の額が少額で、そもそも支払不能ではないときは自己破産できません。
自己破産は「どう努力しても支払いができない状態にある人」を対象とした救済措置のひとつであり、誰もが自由に利用できるわけでない点に注意しましょう。
債務があって苦しんでいても、まずは資産や労働力を使ってコツコツ返済していく自己努力が求められます。
税金の滞納や保険料の滞納しかない
滞納した税金・社会保険料などは「非免責債権」に該当するため、債務がこれしかない場合は自己破産できません。
同様に、損害賠償金・慰謝料・養育費なども「非免責債権」に該当するので注意しましょう。
自己破産しても非免責債権である金額は免除されないため、自己破産する意味がありません。
非免責債権も非免責債権以外も含む申請であれば申請が通るかもしれませんが、完全に借金をゼロにすることはできない点に注意しましょう。
浪費やギャンブルの借金が大部分を占める
過度な浪費・ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当するため、自己破産できません。
自己破産とは本来「やむを得ない事情により借金が膨らんでしまった人」を救済するための措置として施行されています。
自己責任の割合が高い浪費・ギャンブルが原因の場合、「同情の余地がない」と思われてしまうのです。
ただし、ギャンブル依存症やショッピング依存症の治療中であり、医師からの診断・指示が別に出ている場合は考慮してもらえる可能性があります。
過去7年間に自己破産したことがある
過去7年間に自己破産したことがある場合、もう一度自己破産することはできません。
一度救済してもらっても繰り返し借金を作ってしまう人の場合、もはや自己責任であるとみなされてしまいます。
また、7年が経過していても2回目の自己破産申請時には前回より厳しい基準が設けられるので注意しましょう。
どうしても借金せざるを得ない理由がない限り、2度目の申請はかなりハードルが高くなります。
裁判所への予納金が払えない
裁判所への予納金が払えない場合、自己破産の手続き自体を進めることができません。
予納金とは自己破産にかかる費用のことで、手続きをする際に最低限必要なお金です。書類発行にかかる費用、裁判官の人件費、官報公告費用、手数料などが含まれます。
自己破産における予納金は、申請者の状況に応じて決定されます。
資産も収入もなくかなり切羽詰まっている場合、予納金は1万円前後になることが多いです。
反対に、処分できる財産がまだある場合は20万円程かかることもあり、人による差が大きいのが特徴です。
自己破産ができない確率は?
自己破産ができない確率は2%以下と言われています。
非免責債権や免責不許可事由など除外項目があるとはいえ、自己破産申請のほとんどが認められていることがわかります。
これには、「もう借金の返済はできないという状況のなかで新たに人生をスタートさせる方法」という自己破産の性質が関係しています。
切羽詰まった人を見捨ててしまうとより状況が悪化してしまうことを考えると、自己破産を認めるしかないことも多いのです。
2020年の調査結果では不許可はゼロ
2020年の調査結果を見ると、自己破産申請をして「不許可」だったケースはゼロだとわかりました。
| 免責申立の結果 | 20年調査 | 17年調査 | 14年調査 | 11年調査 | 8年調査 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 | 96.85% | 96.77% | 96.44% | 96.67% | 97.85% | 96.91% |
| 不許可 | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 0.16% |
| 却下・棄却 | 0.16% | 0.08% | 0.24% | 0.08% | 0.08% | 0.16% |
| 取り下げ | 1.37% | 2.34% | 2.75% | 2.11% | 1.57% | 2.02% |
| 死亡終了 | 0.32% | 0.08% | 0.32% | 0.24% | 0.08% | 0.20% |
| 不明 | 1.29% | 0.16% | 0.24% | 0.65% | 0.25% | 0.51% |
つまり、自己破産を申請して認められなかった人はゼロ人だった、ということです。
「自己破産ができない確率2%」に含まれているのは、ほとんどが本人による取り下げや死亡終了が中心とわかりました。
自己破産申請が通らないことは、あまり心配しすぎなくてよいでしょう。
ギャンブルや浪費が原因の場合でも、よほどのケースを除き許可されているのが現状です。
自己破産しない方がいい3つのケース
自己破産は債務を見直して計画的な資金計画にする大切な制度ですが、自己破産しない方が良いケースも存在します。
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 資格制限のある職業に就いている
- 持ち家などどうしても残したい財産がある
上記に該当する場合、自己破産には慎重になった方がよいでしょう。
保証人に迷惑をかけたくない
自己破産をしても、連帯保証人や保証人(通常保証人)の支払義務はなくなりません。
債務者である自分が自己破産してしまった場合、当然ながら返済義務は連帯保証人・保証人(通常保証人)へと移ります。
自分の借金を完全に肩代わりさせてしまうことになるため、保証人に迷惑をかけたくないときの自己破産は慎重になった方がよいでしょう。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、「催告抗弁権」を持たない保証人のこと。主債務者と同じ立場でお金を借りている状態になるため、主債務者の資産状況と関係なく返済する義務を負います。
つまり、連帯保証人は自己破産の有無と関係なく返済義務を有しているのが特徴です。
極論、主債務者が支払い負担を避けるため夜逃げしてしまったり、借金の返済をなあなあにして踏み倒したりするだけでも、連帯保証人に請求される可能性があります。
自己破産したとなればほぼ確実に連絡されるだけでなく、全額の一括返済が求められるケースもあるので注意しましょう。
保証人(通常保証人)とは
保証人(通常保証人)とは、「催告抗弁権」を持つ保証人のこと。催告抗弁権とは、保証人(通常保証人)が債権者から債務の履行を請求された際、先に債務者に対して返済を請求するように請求できる権利のことです。
つまり、連帯保証人であれば、保証人になっている分の返済を求められても「先に本人へ請求してくれ」と依頼できます。
とはいえ連帯保証人も保証人(通常保証人)も、もともとお金を借りている主債務者が返済不能に陥ったときは、自分で返済する義務を持ちます。
自己破産が認められるケースはよほど資産状況が悪化していると考えられるので、どちらの保証人でも借金の肩代わりが必要となってくるでしょう。
| 比較項目 | 連帯保証人 | 保証人 |
|---|---|---|
| 責任 | ほぼ主債務者と同じ | 保証債務(主債務者と別) |
| 返済時期 | 請求された時 | 主債務者が返済困難であるとき |
| 危険範囲 | 借りたお金の全額 | 保証人の人数で割った金額 |
| 差押え | 反論できない | 主債務者の後 |
他にも、連帯保証人と保証人(通常保証人)との間には、返済するべき時期や危険範囲の差があります。
より責任が重く、問答無用で請求されてしまうのが連帯保証人と考えておくとよいでしょう。
ただし、連帯保証人・保証人(通常保証人)つきの借金だけを優先的に返済することは「偏頗弁済」に当たり、自己破産手続きができなくなる恐れがあります。
偏頗弁済とは
「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とは、借金の返済ができなくなっているにもかかわらず、一部の債権者にだけ優先的に返済や担保提供などをしてしまうことです。
自己破産や個人再生をするときは全ての債務者を平等に扱う必要があるため、特定の債務だけを優先して返済するおとはできません。
「保証人に迷惑をかけたくないから先に返済しておこう」という打算はほぼ認められないと考えましょう。
資格制限のある職業に就いている
資格制限のある職業に就いている場合、自己破産することで一定期間資格や職業の制限を受けることがあります。
資格制限とは
「資格制限」とは、一時的に資格の取得・登録や資格を使った仕事ができなくなること。破産法ではなく各資格・職業に関する法律に規定されており、自己破産者となることで仕事に制限が加えられます。
資格制限のある代表的な職種は、以下の通りです。
| 分類 | 資格・職業 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 士業 | 弁護士 | 弁護士法7条4号 |
| 弁理士 | 弁理士法8条10号 | |
| 公認会計士 | 公認会計士法4条4号 | |
| 税理士 | 税理士法4条2号 | |
| 司法書士 | 司法書士法5条3号 | |
| 行政書士 | 行政書士法2条の2第3号 | |
| 社会保険労務士 | 社会保険労務士法5条2号 | |
| 土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法5条3号 | |
| 通関士 | 通関業法第31条第2項1号 |
いわゆる「士業」と呼ばれる専門職では、ほとんど資格制限が適用されてしまいます。
自己破産の申立から4~6ヶ月程度で資格制限が解除されるのがほとんどですが、詳細は自身の資格に関連する根拠法令を参照しながら確認しましょう。
なお、資格制限が適用された場合、当然ながらその期間中は資格が必要な仕事や「独占業務」ができません。
独占業務とは
「独占業務」とは、その資格を持っていないとできない業務のこと。わかりやすい例でいうと、弁護士における裁判書類作成、医師・看護師等による医療行為が該当します。
資格制限を受けたからといって即座に解雇されることはないものの、実務が大幅に制限されてしまうため、自己破産の事実が職場に知れ渡ってしまうことも多いです。
また、直接的な人事評価はされずとも、「私生活に不安がある」「期間中の実務に大きな穴を作った」という印象が査定に影響するケースも少なくありません。
自己破産期間中は本当にサポート業務を担当するだけで問題ないか、自分の仕事を振り返りながらシミュレーションしてみましょう。
自己破産できないときはどうする?
最後に、自己破産できないときの対策を紹介します。
- 安定した収入があれば個人再生を検討する
- 裁判所を通さず任意整理で交渉する
「自己破産ができなかったから人生終わった…」と考える必要はありません。
他にも債務の見直しをする手法があるので、下記を確認してみましょう。
安定した収入があれば個人再生を検討する
安定した収入があれば、個人再生がおすすめです。
個人再生とは
「個人再生」とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手法のこと。
個人再生は返済が必要な金額を概ね5分の1程度にまで圧縮できるのが特徴であり、残った金額についてはその後も継続して返済を続けていきます。
自己破産と違って資格制限や財産処分を受ける必要がなく、実生活への影響を最小限に抑えられるのが強みです。
| 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 借金減額 | 概ね5分の1まで圧縮 | 全額免除 |
| 家について | 住宅ローン特則が利用できる場合は、手放さなくてOK | 処分される |
| 車について | ローンが残っていたら、手放す可能性あり | ローンが残っていない場合でも、時価が20万円超の場合は処分対象となる |
| 資格制限 | なし | あり |
| 免責不許可事由 | なし | あり |
自己破産のようにギャンブルによる借金などの免責不許可事由などがないのもメリットのひとつ。
なお、個人再生後に残る返済額については、以下3つの要素から決定されます。
| ①負債額から算出する金額(最低弁済基準) | 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額 負債額が100万円以上500万円以下の場合は、100万円 負債額が500万円超1500万円以下の場合は、負債額の5分の1 負債額が1500万円超3000万円以下の場合は、300万円 負債額が3000万円超5000万円以下の場合は、負債額の10分の1 |
|---|---|
| ②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準) | 不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額。 |
| ③収入から算出する金額 | 収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額。 |
資産も収入もなく完全に返すアテがないのであれば自己破産するしかありませんが、収入があるときは個人再生の方がダメージを減らせるのでおすすめです。
裁判所を通さず任意整理で交渉する
裁判所を通さず、任意整理として交渉しながら返済額を減らしていく方法もあります。
任意整理とは
「任意整理」とは「債務整理」とも呼ばれる手法であり、弁護士が貸付業者と交渉することで返済額を減額してもらう手続きのこと。
原則として利息の交渉をして返済額を抑える手法であり、元本そのものは減らない点に注意が必要です。
個人再生と違って一部の債権者だけと交渉することもできるので自由度が高く、裁判所を介さないため手続きも比較的容易です。
| 任意整理 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 裁判所 | 裁判所を介さない | 裁判所を介する |
| 債務の減額 | 利息が減額されるのみで元本は減らない | 全額免除 |
| 毎月の返済 | 月々の支払が軽くなる | 返済不要になる |
| 財産処分 | なし | あり |
| 保証人への影響 | なし | あり |
とはいえ自分ひとりで任意整理をするハードルが高い!と感じる人も多いので、困ったときは弁護士に相談しましょう。
その他、簡易裁判所における訴訟代理権を付与された「認定司法書士」と呼ばれる司法書士であれば、債権額140万円以下の任意整理に限り担当できます。
まとめ
「本当に首が回らなくなったら自己破産すればいい」と考える人もいますが、実は自己破産したくてもできないケースがあるので注意が必要です。
特に、借金の内容や理由によっては申請が却下されてしまうこともあるので、事前に条件を確認しておくことが大切です。