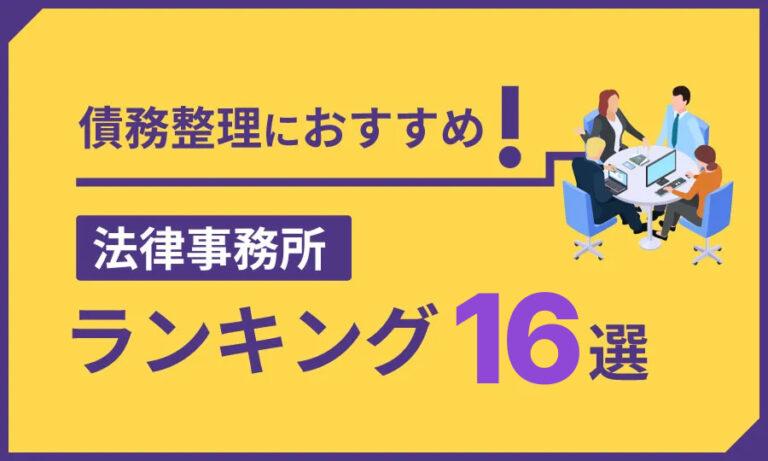法人破産の着手金はいくら?費用相場を解説

会社などの経営が上手くいかなくなった場合に行う法人の倒産処理手続きの中で、会社の再建を諦めて清算してしまうのが破産手続きです。では、法人の破産手続きをするのには、いくらくらいの費用が必要となるのでしょうか。
本記事では、法人破産にかかる費用についてお伝えします。
※本記事は法人の自己破産を前提とする記事です
法人破産の着手金の相場は規模にもよるが50〜100万円
まず、法人破産を弁護士に依頼する場合の着手金には、50~100万円程度の費用がかかります。
法人破産については、手続きを行うにあたって複雑な破産法、破産法の基本になる民法・会社法などの取引・法人運営に関する法律、裁判所に申立てをするための実務的な知識など、様々な知識が欠かせません。
本来、きちんと全額契約通り返済すべき債務について履行せずに会社・法人を消滅させる法人破産をする以上、債権者を平等に扱う、資産関係を明確にするなど、厳格なルールに従う必要があります。
そのため、弁護士に依頼をしての手続きが必要です。
その弁護士に依頼するには、着手金の支払いが不可欠です。
その着手金は、規模に応じて50~100万円程度かかります。複雑な案件の場合、さらに高額になる場合があります。
金額が多くなるのは次のような場合です。
- 会社財産の種類が多い
- 負債の規模が大きい
- 債権者の数が多い
着手金については分割で支払うことができる場合があるので、法律相談の際、弁護士へ相談してみましょう。
- 法人破産で弁護士に納める費用は主に3種類
- 裁判所へ納める予納金も忘れず認識しておく
- 法人と代表者の同時破産は別途費用がかかる
- 同時破産すると裁判所への予納金が節約できる
- 安いだけで弁護士を選ぶと後悔する
それぞれ順に解説します。
法人破産で弁護士に納める費用は主に3種類
法人破産にかかる費用で着手金の他に納める費用は主に次の3種類です。
- 法律相談料
- 報酬金
- その他実費等の費用
それぞれどれくらいの費用がかかるかを確認してみましょう。
「相談料」は弁護士事務所によっては無料の場合も
案件の依頼を決めている場合でも、まずは弁護士に相談をします。
相談料(事務所によって法律相談・借金相談など異なります)は、30分5,000円~程度が相場となっており、法人破産の場合には1時間以上の相談になることが多く10,000円~程度が必要です。
ただし、個人・法人を問わず借金問題を中心に取り扱っている弁護士事務所であれば、相談料については個人と同様に無料としているところもあります。
市区町村役場で行われている弁護士相談などを利用する場合も無料で相談できる場合があるのですが、30分程度の時間が限られた相談時間しかないので、詳細な相談ができない可能性が高いです。
「着手金」と「報酬金」がセットの場合もある
依頼をする時の弁護士費用となるのが着手金で、これと合わせて破産手続きが無事終わった後に支払うのが報酬金です。
着手金と報酬金については、請求するタイミングが別々になるので、本来は別に支払われます。
弁護士事務所によっては、着手金・報酬金という分け方をせずにセットで弁護士費用などの名目で請求されることもあります。
この場合、弁護士費用はトータルで50~100万円となるように調整されるのが通常です。
例えば、50万円程度が相場となる案件である場合、弁護士費用として最初に50万円程度が請求されるか、着手金として30万円・報酬金として20万円が請求されるかのどちらかです。
報酬金の支払いをする場合、実質的には法人の代表者がその支払いをします。
「実費」は印紙や切手など必ずかかる費用
弁護士に支払う費用としては、実費の支払いも求められます。
破産手続きの代理人として弁護士が職務を行うにあたって、次のような費用のかかることを行うことが必要です。
- 依頼者や債権者・裁判所・破産管財人との電話でのやりとり
- 裁判所・破産管財人への書面のFAX送信
- 依頼者・債権者・裁判所・破産管財人に書面を送る際の郵便料金
これら実費については弁護士が依頼者に請求します。
実費については、案件ごとに管理して逐一請求する場合もありますが、多くのケースで「事務手数料」などの名目で概算で請求することがあります。
弁護士事務所のホームページに記載していることもあれば、契約時までわからないこともあるので、不明である場合には契約時に弁護士に確認してみましょう。
裁判所へ納める予納金も忘れず認識しておく

破産手続きについては、弁護士費用のみならず、裁判所に納める費用もあります。
裁判所に納める費用には次の3つの種類があります。
- 申立手数料
- 予納郵券
- 予納金
申立手数料
法人破産の手続きは裁判所に申立てて行うので、手数料がかかります。
申立手数料は一律1,000円です。
申立手数料は、申立書に1,000円の収入印紙を貼ることで納めます。
予納郵券
裁判所への申し立て時に、裁判所が郵送に使用するための切手を購入して納付する必要があります。
この納める切手のことを予納郵券と呼んでおり、裁判所によって5,000円~10,000円程度の指定された郵券を購入して納付します。
例えば、東京地方裁判所の場合は4,400円分(210円切手×8枚、140円切手×1枚、84円切手× 29枚、10円切手×12枚、2円切手×10枚、1円切手×4枚)を納入します(※参考:破産事件の手続き費用一覧|裁判所)。
弁護士に依頼すれば弁護士が購入をしますので、依頼者がこれらの切手を購入する必要はありません。
予納金
破産手続きでは、国の機関紙である官報に公告が行われます。
官報に公告するための費用として予納金という形で、裁判所によって15,000円前後の費用を納入する必要があります(参考:破産事件の手続き費用一覧|裁判所)。
少額管財事件で20万円程の予納金
もう一つの種類の予納金として、引継予納金があります。
破産手続きでは裁判所から選任される破産管財人が手続きを主導します。
この破産管財人に対する報酬となる費用として、引継予納金という名目で支払いが求められます。
引継予納金は事件の種類によって異なります。
債務の額が5,000万円以内で、簡易な手続きで終わらせられる少額管財事件では、引継予納金は20万円程度です。
少額管財は弁護士に依頼して申立てをする場合に利用が可能で(同じように債務整理に対応している司法書士では不可)、申立てにあたって丁寧に財産関係などを調査しており、破産管財人の負担が少ないことから費用が後述する通常管財(特定管財)よりも安くなっています。
通常管財事件では70万円程
通常管財事件(特定管財事件とも呼ばれます)では、法人破産の場合には負債の額によって次の通りです。
| 負債の額 | 引継予納金の額 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 70万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ |
なお、この額については事案に応じて増減することがあります。
少額管財かつ東京地裁の場合は予納金20万円の4回分割納付が認められることがありますが、通常管財事件では分割は認められていません。通常はこれらの費用を事前に積み立てをして、納入ができる状態になってから破産手続きを申し立てます。
法人と代表者の同時破産は別途費用がかかる
法人破産を行うような場合、会社の代表者も会社の運転資金の捻出のために個人で借入をしたり、会社の債務について連帯保証人となっていることがあります。
そのため、法人破産を行う場合には、代表者個人に資力がない場合は代表者も同時に破産手続きを行います(代表者個人の自己破産手続き)。
手続きとしては同時に行うことになるのですが、法人と個人でそれぞれ契約する必要なので、それぞれ費用がかかります。
また、ケースによっては、親族が保証人となっていたり、代表者が契約者となっている住宅ローンについて保証人となっている親族がいる、などの場合に、同時に自己破産が必要となるようなケースもあります。
自己破産手続きについては、別途30万円~50万円程度の費用がかかります。
同時に手続きができることから費用を安く抑えているようなケースもあるので、弁護士に相談してみましょう。
同時破産すると裁判所への予納金が節約できる
法人と代表者が同時に破産する場合には、「法人と代表者で別々に予納金を20万円以上用意しなければならない」というルールはないため、実質的に1件分の予納金で済む場合があります。そのため、破産管財人も運用上、一人が選任されます。
また、上述したような、代表者の親族が同時に破産するケースでも、実質的に1件分の予納金で済む場合があります。
安いだけで弁護士を選ぶと後悔する
法人としての経営が上手くいっておらず、債権者への支払いも難しくなっている、すでに滞ってしまっているようなケースにおいて、弁護士費用はなるべく安いほうがいい、と考えるのもやむを得ません。
このような債務者の窮状に寄り添うために費用を安くしているケースもあります。
しかし、法人破産などの法人の倒産処理手続きについての実績が少ない場合や、懲戒処分を受けているなどの事情で、顧客獲得をしやすいように弁護士費用を著しく下げるようなケースがあります。
法人破産は非常に複雑な手続きであるため、弁護士の経験・知識不足が原因で手続きに不具合が生じるケースがあります。
また、懲戒処分を受けた弁護士の中には、弁護士資格を有しない者に手続きを行わせているような場合もあり、杜撰な手続き進行で損害をあたえる場合もあります。
弁護士費用が安いだけで選ぶのではなく、きちんと手続きを成功に導ける弁護士かどうか、取扱い実績などを慎重に調べてから依頼を検討しましょう。
法人破産の着手金が払えないときは?

法人破産の着手金が払えないときはどのようにすれば良いのでしょうか。
上述したように法人破産の着手金については、事案により50万円~100万円以上必要であるなど、非常に高額の費用が必要です。
法人破産をしなければならないような状態に陥っている場合に、この支払いを一括ですることは非常に困難であることが多く、何らかの対策が必要です。
その対策として次のようなものが挙げられます。
それぞれについて順に解説いたします。
法人の財産を処分する
法人の財産を処分して着手金の支払いをするのが一つの方法です。
法人にまだ財産が残っているような場合には、その財産を処分することで現金を捻出することができます。
ただし、法人の財産の処分には慎重な配慮が必要です。
例えば、売却が難しいからといって、安易に廉価に売却をした場合、破産法160条1項1号の否認権の対象となる可能性や、破産法265条1項4号に該当して詐欺破産罪に問われる可能性があります。
また個人の自己破産について、破産法252条1項1号で免責不許可事由とされる可能性もあります。
否認権の対象になると、破産手続開始決定後に破産管財人から売却行為を否認され、買い主から責任追及される可能性があります。
また、詐欺破産罪として、逮捕・起訴をされてしまう可能性もあります。
特に、個人の自己破産について免責不許可事由とされ、破産法252条2項所定の裁量免責を得られなければ、個人が負っている債務を引き続き負います。
法人の財産を処分して弁護士費用として捻出する場合、売却が廉価での売却では無いことや、売却代金の使途などを客観的に証明できるようにする必要があるので、弁護士に相談しながら行いましょう。
売掛金などの債権を回収する
売掛金などの債権を回収するなどの方法も弁護士費用を捻出する方法の一つです。
会社の動産や不動産だけではなく、売掛金・未収金といった債権についても同様に会社の財産です。
未回収となっている債権を回収することで費用が捻出できる場合には、未回収となっている債権の回収を行いましょう。
支払い時期が将来となっている債権について、債務者が任意に支払ってくれる場合には、履行期よりも前に回収し支払いに充てても良いでしょう。
また、履行期が先であり、債務者も本来の履行期までは支払える状態ではない場合に、債権の買い取りをしてくれるファクタリングが利用されることがあります。
その利用については、割引率があまりにも低い場合には、債権という会社の財産を毀損させたとして、否認権・詐欺破産罪・免責不許可事由となる可能性もあります。
債権回収にあたっても依頼をする予定の弁護士に相談しながら行いましょう。
分割払いができる弁護士事務所を探す
着手金・弁護士費用を分割払いができる弁護士事務所を探しましょう。
着手金・弁護士費用は高額ですが、その支払いは必ず一括でなければならないわけではありません。
着手金の支払いについて、企業の案件については一括で支払うことも多いのですが、法人破産のような案件では分割での支払いを認めているケースもあります。
すでに法人が破綻してしまっている場合には、仕事を探して得られた給与から分割して弁護士費用を支払うことが認められることも多いです。
費用の支払い方法については、多くのケースで弁護士が開設しているホームページに記載があったり、質問をするためのメールフォームやチャットなどが用意されていますので、事前に確認してみると良いでしょう。
法人破産の着手金はいくら?費用相場を解説

会社などの経営が上手くいかなくなった場合に行う法人の倒産処理手続きの中で、会社の再建を諦めて清算してしまうのが破産手続きです。では、法人の破産手続きをするのには、いくらくらいの費用が必要となるのでしょうか。
本記事では、法人破産にかかる費用についてお伝えします。
※本記事は法人の自己破産を前提とする記事です
法人破産の着手金の相場は規模にもよるが50〜100万円
まず、法人破産を弁護士に依頼する場合の着手金には、50~100万円程度の費用がかかります。
法人破産については、手続きを行うにあたって複雑な破産法、破産法の基本になる民法・会社法などの取引・法人運営に関する法律、裁判所に申立てをするための実務的な知識など、様々な知識が欠かせません。
本来、きちんと全額契約通り返済すべき債務について履行せずに会社・法人を消滅させる法人破産をする以上、債権者を平等に扱う、資産関係を明確にするなど、厳格なルールに従う必要があります。
そのため、弁護士に依頼をしての手続きが必要です。
その弁護士に依頼するには、着手金の支払いが不可欠です。
その着手金は、規模に応じて50~100万円程度かかります。複雑な案件の場合、さらに高額になる場合があります。
金額が多くなるのは次のような場合です。
- 会社財産の種類が多い
- 負債の規模が大きい
- 債権者の数が多い
着手金については分割で支払うことができる場合があるので、法律相談の際、弁護士へ相談してみましょう。
- 法人破産で弁護士に納める費用は主に3種類
- 裁判所へ納める予納金も忘れず認識しておく
- 法人と代表者の同時破産は別途費用がかかる
- 同時破産すると裁判所への予納金が節約できる
- 安いだけで弁護士を選ぶと後悔する
それぞれ順に解説します。
法人破産で弁護士に納める費用は主に3種類
法人破産にかかる費用で着手金の他に納める費用は主に次の3種類です。
- 法律相談料
- 報酬金
- その他実費等の費用
それぞれどれくらいの費用がかかるかを確認してみましょう。
「相談料」は弁護士事務所によっては無料の場合も
案件の依頼を決めている場合でも、まずは弁護士に相談をします。
相談料(事務所によって法律相談・借金相談など異なります)は、30分5,000円~程度が相場となっており、法人破産の場合には1時間以上の相談になることが多く10,000円~程度が必要です。
ただし、個人・法人を問わず借金問題を中心に取り扱っている弁護士事務所であれば、相談料については個人と同様に無料としているところもあります。
市区町村役場で行われている弁護士相談などを利用する場合も無料で相談できる場合があるのですが、30分程度の時間が限られた相談時間しかないので、詳細な相談ができない可能性が高いです。
「着手金」と「報酬金」がセットの場合もある
依頼をする時の弁護士費用となるのが着手金で、これと合わせて破産手続きが無事終わった後に支払うのが報酬金です。
着手金と報酬金については、請求するタイミングが別々になるので、本来は別に支払われます。
弁護士事務所によっては、着手金・報酬金という分け方をせずにセットで弁護士費用などの名目で請求されることもあります。
この場合、弁護士費用はトータルで50~100万円となるように調整されるのが通常です。
例えば、50万円程度が相場となる案件である場合、弁護士費用として最初に50万円程度が請求されるか、着手金として30万円・報酬金として20万円が請求されるかのどちらかです。
報酬金の支払いをする場合、実質的には法人の代表者がその支払いをします。
「実費」は印紙や切手など必ずかかる費用
弁護士に支払う費用としては、実費の支払いも求められます。
破産手続きの代理人として弁護士が職務を行うにあたって、次のような費用のかかることを行うことが必要です。
- 依頼者や債権者・裁判所・破産管財人との電話でのやりとり
- 裁判所・破産管財人への書面のFAX送信
- 依頼者・債権者・裁判所・破産管財人に書面を送る際の郵便料金
これら実費については弁護士が依頼者に請求します。
実費については、案件ごとに管理して逐一請求する場合もありますが、多くのケースで「事務手数料」などの名目で概算で請求することがあります。
弁護士事務所のホームページに記載していることもあれば、契約時までわからないこともあるので、不明である場合には契約時に弁護士に確認してみましょう。
裁判所へ納める予納金も忘れず認識しておく

破産手続きについては、弁護士費用のみならず、裁判所に納める費用もあります。
裁判所に納める費用には次の3つの種類があります。
- 申立手数料
- 予納郵券
- 予納金
申立手数料
法人破産の手続きは裁判所に申立てて行うので、手数料がかかります。
申立手数料は一律1,000円です。
申立手数料は、申立書に1,000円の収入印紙を貼ることで納めます。
予納郵券
裁判所への申し立て時に、裁判所が郵送に使用するための切手を購入して納付する必要があります。
この納める切手のことを予納郵券と呼んでおり、裁判所によって5,000円~10,000円程度の指定された郵券を購入して納付します。
例えば、東京地方裁判所の場合は4,400円分(210円切手×8枚、140円切手×1枚、84円切手× 29枚、10円切手×12枚、2円切手×10枚、1円切手×4枚)を納入します(※参考:破産事件の手続き費用一覧|裁判所)。
弁護士に依頼すれば弁護士が購入をしますので、依頼者がこれらの切手を購入する必要はありません。
予納金
破産手続きでは、国の機関紙である官報に公告が行われます。
官報に公告するための費用として予納金という形で、裁判所によって15,000円前後の費用を納入する必要があります(参考:破産事件の手続き費用一覧|裁判所)。
少額管財事件で20万円程の予納金
もう一つの種類の予納金として、引継予納金があります。
破産手続きでは裁判所から選任される破産管財人が手続きを主導します。
この破産管財人に対する報酬となる費用として、引継予納金という名目で支払いが求められます。
引継予納金は事件の種類によって異なります。
債務の額が5,000万円以内で、簡易な手続きで終わらせられる少額管財事件では、引継予納金は20万円程度です。
少額管財は弁護士に依頼して申立てをする場合に利用が可能で(同じように債務整理に対応している司法書士では不可)、申立てにあたって丁寧に財産関係などを調査しており、破産管財人の負担が少ないことから費用が後述する通常管財(特定管財)よりも安くなっています。
通常管財事件では70万円程
通常管財事件(特定管財事件とも呼ばれます)では、法人破産の場合には負債の額によって次の通りです。
| 負債の額 | 引継予納金の額 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 70万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ |
なお、この額については事案に応じて増減することがあります。
少額管財かつ東京地裁の場合は予納金20万円の4回分割納付が認められることがありますが、通常管財事件では分割は認められていません。通常はこれらの費用を事前に積み立てをして、納入ができる状態になってから破産手続きを申し立てます。
法人と代表者の同時破産は別途費用がかかる
法人破産を行うような場合、会社の代表者も会社の運転資金の捻出のために個人で借入をしたり、会社の債務について連帯保証人となっていることがあります。
そのため、法人破産を行う場合には、代表者個人に資力がない場合は代表者も同時に破産手続きを行います(代表者個人の自己破産手続き)。
手続きとしては同時に行うことになるのですが、法人と個人でそれぞれ契約する必要なので、それぞれ費用がかかります。
また、ケースによっては、親族が保証人となっていたり、代表者が契約者となっている住宅ローンについて保証人となっている親族がいる、などの場合に、同時に自己破産が必要となるようなケースもあります。
自己破産手続きについては、別途30万円~50万円程度の費用がかかります。
同時に手続きができることから費用を安く抑えているようなケースもあるので、弁護士に相談してみましょう。
同時破産すると裁判所への予納金が節約できる
法人と代表者が同時に破産する場合には、「法人と代表者で別々に予納金を20万円以上用意しなければならない」というルールはないため、実質的に1件分の予納金で済む場合があります。そのため、破産管財人も運用上、一人が選任されます。
また、上述したような、代表者の親族が同時に破産するケースでも、実質的に1件分の予納金で済む場合があります。
安いだけで弁護士を選ぶと後悔する
法人としての経営が上手くいっておらず、債権者への支払いも難しくなっている、すでに滞ってしまっているようなケースにおいて、弁護士費用はなるべく安いほうがいい、と考えるのもやむを得ません。
このような債務者の窮状に寄り添うために費用を安くしているケースもあります。
しかし、法人破産などの法人の倒産処理手続きについての実績が少ない場合や、懲戒処分を受けているなどの事情で、顧客獲得をしやすいように弁護士費用を著しく下げるようなケースがあります。
法人破産は非常に複雑な手続きであるため、弁護士の経験・知識不足が原因で手続きに不具合が生じるケースがあります。
また、懲戒処分を受けた弁護士の中には、弁護士資格を有しない者に手続きを行わせているような場合もあり、杜撰な手続き進行で損害をあたえる場合もあります。
弁護士費用が安いだけで選ぶのではなく、きちんと手続きを成功に導ける弁護士かどうか、取扱い実績などを慎重に調べてから依頼を検討しましょう。
法人破産の着手金が払えないときは?

法人破産の着手金が払えないときはどのようにすれば良いのでしょうか。
上述したように法人破産の着手金については、事案により50万円~100万円以上必要であるなど、非常に高額の費用が必要です。
法人破産をしなければならないような状態に陥っている場合に、この支払いを一括ですることは非常に困難であることが多く、何らかの対策が必要です。
その対策として次のようなものが挙げられます。
それぞれについて順に解説いたします。
法人の財産を処分する
法人の財産を処分して着手金の支払いをするのが一つの方法です。
法人にまだ財産が残っているような場合には、その財産を処分することで現金を捻出することができます。
ただし、法人の財産の処分には慎重な配慮が必要です。
例えば、売却が難しいからといって、安易に廉価に売却をした場合、破産法160条1項1号の否認権の対象となる可能性や、破産法265条1項4号に該当して詐欺破産罪に問われる可能性があります。
また個人の自己破産について、破産法252条1項1号で免責不許可事由とされる可能性もあります。
否認権の対象になると、破産手続開始決定後に破産管財人から売却行為を否認され、買い主から責任追及される可能性があります。
また、詐欺破産罪として、逮捕・起訴をされてしまう可能性もあります。
特に、個人の自己破産について免責不許可事由とされ、破産法252条2項所定の裁量免責を得られなければ、個人が負っている債務を引き続き負います。
法人の財産を処分して弁護士費用として捻出する場合、売却が廉価での売却では無いことや、売却代金の使途などを客観的に証明できるようにする必要があるので、弁護士に相談しながら行いましょう。
売掛金などの債権を回収する
売掛金などの債権を回収するなどの方法も弁護士費用を捻出する方法の一つです。
会社の動産や不動産だけではなく、売掛金・未収金といった債権についても同様に会社の財産です。
未回収となっている債権を回収することで費用が捻出できる場合には、未回収となっている債権の回収を行いましょう。
支払い時期が将来となっている債権について、債務者が任意に支払ってくれる場合には、履行期よりも前に回収し支払いに充てても良いでしょう。
また、履行期が先であり、債務者も本来の履行期までは支払える状態ではない場合に、債権の買い取りをしてくれるファクタリングが利用されることがあります。
その利用については、割引率があまりにも低い場合には、債権という会社の財産を毀損させたとして、否認権・詐欺破産罪・免責不許可事由となる可能性もあります。
債権回収にあたっても依頼をする予定の弁護士に相談しながら行いましょう。
分割払いができる弁護士事務所を探す
着手金・弁護士費用を分割払いができる弁護士事務所を探しましょう。
着手金・弁護士費用は高額ですが、その支払いは必ず一括でなければならないわけではありません。
着手金の支払いについて、企業の案件については一括で支払うことも多いのですが、法人破産のような案件では分割での支払いを認めているケースもあります。
すでに法人が破綻してしまっている場合には、仕事を探して得られた給与から分割して弁護士費用を支払うことが認められることも多いです。
費用の支払い方法については、多くのケースで弁護士が開設しているホームページに記載があったり、質問をするためのメールフォームやチャットなどが用意されていますので、事前に確認してみると良いでしょう。